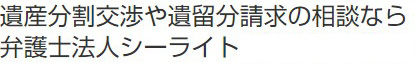生前贈与と相続~特別受益の対象となる場合とならない場合~

被相続人から生前に現金や不動産などの贈与を受けた相続人がいる場合には、相続発生後の特別受益の問題や遺留分の問題などの場面で贈与価額の評価額を算定する必要があります。
今回は、生前贈与があった場合に、相続時、特別受益にあたるのかどうかの問題や生前贈与があった場合にこんなケースでは相続はどうなるのかといった事例などをご紹介します。
目次
生前贈与が特別受益にあたるのかどうか
「生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるかどうか」というのは、つまりは「特別受益の対象となるのかどうか」です。民法903条1項では、婚姻や養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与が特別受益にあたると規定しています。
では、それぞれの贈与についてもう少し詳しく述べていきましょう。
婚姻のための贈与
婚姻の際の持参金や支度金については、一般的に特別受益になるとされています。ただし、その額が少額の場合、被相続人の資産および生活状況と照らし合わせて扶養の一部と認められるようなときには、特別受益にはあたらないと考えられます。また、結納金や挙式費用については、被相続人である親が支出した場合、一般的には、これらの費用は特別受益にはあたらず、単なる契約費用と考えられます。
養子縁組のための贈与
養子縁組を行う際に、血縁上の親が子どもに持参金を贈与すれば、それは特別受益の対象となります。
生計の資本としての贈与
居住用の不動産の贈与や不動取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与など、生計の基礎として役立つような財産の給付が、生計の資本としての贈与になります。
この生計の資本であるかどうかについては、贈与金額や贈与の趣旨などから判断することになります。夫婦間の生活保持義務、親族間の扶養義務の範囲内のものと評価される場合には特別受益に含まれません。相続分の前渡しであると認められる程度に高額の贈与は、原則として特別受益になり得ると考えられます。そのため、短期間で使われた少額の贈与については、生計の資本としての贈与として判断することが難しいです。
では、一回あたりの金額は少額でも、長期間にわたって贈与が行われ、結果的に合計金額が高額となった場合には、生計の資本としての贈与として、特別受益であると判断してよいのかが問題となります。この点については、各贈与の時に、被相続人からの扶養的な金銭援助と考えられる場合、一定金額を超えている部分についてのみ特別受益の対象とするという調停が成立した事例があります。
では次に、上記以外のケースの場合には生前贈与として、特別受益の対象となるのかどうかもご紹介します。
学費について
よく特別受益にあたるのかどうかで問題になるのが、学費になります。
高等教育のための教育費(入学金や授業料など)は、被相続人が扶養義務者である場合には、扶養義務の履行に基づく支出と考えられるので、特別受益にはあたりません。また、高校卒業後に専門学校、大学、海外留学などに進学した場合の教育にかかる費用についても、医学部や薬学部など特別に多額な場合を除いて、扶養義務の履行に基づく支出と考えられます。
また、子どもに対しての扶養の範囲内とは言い難い金額の贈与であっても、相続人全員が、同額に近い受益を受けていたり、全員大学教育を受けていたりする場合などには、特別受益として考慮しないとするのが相当とされています。
そのため、特別受益にあたるのかどうかを判断するためには、被相続人の生活状況と資産の状況を考慮することも必要になります。
相続人の債務について
相続人が負っている借金などの債務を被相続人が代わりに支払った場合には、これが特別受益にあたるのかどうかを考えてみたいと思います。実際に起こった裁判例を紹介します。
このことに関して、被相続人は、その夫に返済を求めなかった(これを求償権の放棄といいます)という事実があり、それは、相続分の前渡しとして、生計の資本としての贈与であると解釈されるとしました。
ここでのポイントは、金銭の支払いは、被相続人の補償債務を履行し、その反面夫に対する求償権を取得するため、特別受益にはあたらないが、共同相続人の夫に対して返済を求めなかったことは、求償権の放棄にあたり、これが共同相続人に対しての生計の資本としての贈与と解釈され、特別受益の持戻しにあたると判断されました。
つまり、求償権を放棄したと認める事情としては、長い期間、求償権を行使しないまま放置されている状態などが考えられます。
祝い金について
たとえば、入学祝い、誕生祝い、新築祝い、出産祝いなど、被相続人が親であれば通常の援助範囲内でなされた祝い金の贈与は、特別受益にあたりません。これは、扶養義務に基づく援助と考えられるためです。
独立して生活することが難しい子どもへの援助について
精神的な要因や身体的な要因により独立して生活を送ることが難しい子どもに対して、被相続人である親が扶養義務に基づいた援助を行うことは、特別受益にはあたりません。
ここまで、特別受益とみなされる生前贈与とそうでないものの例をあげてきました。では、特別受益にあたるとされる生前贈与は、かならず遺産分割の際には持戻しを行う必要があるのでしょうか。
特別受益の持戻し免除
被相続人が、遺言などで持戻しを免除する意思表示をしている場合には、特別受益の持戻しはしなくてよくなります。意思表示の方法に特別の定めはありません。そのため、贈与と同時でもそうでなくてもよく、また明示でも黙示でもその伝え方は問われません。特別受益の持戻しが免除された場合には、生前贈与を遺産に含めず相続開始時の遺産を相続分で分割することになります。
また、平成30年7月の法改正で、配偶者については、一定の条件を満たせば居住用不動産に関して特別受益の持戻し免除の意思表示があったと推定されるようになりました。
一定の条件とは、「20年以上の婚姻期間」と「配偶者に対する居住用不動産の遺贈もしくは贈与があった場合」となります。この場合には、配偶者に遺贈もしくは贈与された居住用不動産に関しては遺産分割の対象とはなりません。
特別受益の持戻しについては、注意すべき点があり、持戻さないのは遺産分割時のみとなります。そのため、遺留分を計算する際には、持戻し免除が適用されず、持戻し免除された特別受益も含めて計算することになります。
生前贈与と遺留分の関係については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
相続開始時の贈与の価値について
生前贈与を特別受益として持戻す場合には、その価値は、相続開始時を基準として評価することになります。金銭の場合には、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算して評価します。また、不動産や動産の場合も、相続開始時の価額に換算して評価することとなります。
たとえば生前贈与時に2,000万円、相続開始時に2,800万円、遺産分割時に2,900万円の価値がある不動産を生前贈与された場合には、相続開始時の時価である2,800万円を基準として評価します。
具体例
X(被相続人)が亡くなり、相続は、妻のWと子どもA・B・Cでした。
Xの遺産総額は、1億6,000万円です。Xは、生前に子どもAに対して、500万円の贈与をしていました。この贈与は、相続開始時の価額に換算すると2,000万円となります。
また、Xは、遺言で2,000万円をWに遺贈するとしていました。
この場合のそれぞれの具体的な相続割合はどのようになるのでしょうか。
生前贈与は、持戻しの対象となり、みなし相続財産の総額は、1億8,000万円(1億6,000万円+2,000万円)となります。
遺贈された2,000万円については、遺産1億6,000万円の中に含まれていることに注意します。このみなし相続財産1億8,000万円を各共同相続人の相続分で分けます。
W:1億8,000万円×1/2=9,000万円
A:1億8,000万円×1/6=3,000万円
B:1億8,000万円×1/6=3,000万円
C:1億8,000万円×1/6=3,000万円
次に特別受益を控除します。この事例において問題となるのは、Wの遺贈とAの贈与です。
W:9,000-2,000=7,000万円
A:3,000-2,000=1,000万円
もともとの遺産から遺贈を分けます。
1億6,000万円-2,000=1億4,000万円
この遺贈される2,000万円については、相続開始時にWへ移転することになります。
その結果、遺贈を除いた遺産1億4,000万円は、各相続人が下記のような割合で割り当てられたことになります。
W:A:B:C=7,000:1,000:3,000:3,000=7:1:3:3
ではもし、ある相続人が、予定される相続分から特別受益を控除する計算をした結果、相続分がゼロまたはマイナスとなった場合についてはどうなるのでしょうか。このような場合には、相続財産から現実に取得できる相続分はなしということになります。しかし、計算の結果マイナスとなった場合でも、超過受益分を返還する必要はなく、具体的な相続分はゼロということになるだけです。
次に贈与財産が相続開始時に失われてしまった場合には、どのような評価をされるのかをご紹介します。この場合には、受贈者の行為により贈与財産が失われた場合なのか、価額が変動したなど受贈者の行為によらない場合なのかで変わってきます。
受贈者の行為による場合
たとえば、被相続人から不動産を生前贈与されていたが、被相続人の死亡時にその不動産は、転売されておりすでにその贈与を受けた相続人の所有下にないケースを考えてみます。
不動産の価格は、贈与時と相続開始時では変動していたと仮定します。
このようなケースでは、受贈者の行為により贈与された不動産の所有権が失われているため、その変化については無視することになります。つまり、実際には転売されている不動産も、そのまま存在するものと仮定され、相続開始時点の価額に換算して評価されることになります。
他にも、贈与された独立資金としての現金を用いて土地を購入した場合などが考えられますが、このケースにおいても同様に現金が存在すると仮定され、相続開始時の価値に換算され評価されることになります。
受贈者の行為によらない場合
建物を生前贈与されたけれども、大震災により焼失してしまったケースなど、贈与財産が不可抗力により滅失してしまった場合は、受贈者は財産の贈与を受けなかったものとして算定されるのが妥当と考えられています。
※ただし、他の相続人との公平を確保するために、相続開始時にも原状のまま存在するものと仮定して評価されるべきという見解も一方で存在します。
また、贈与財産の価額が不可抗力によらず増減した場合は、相続開始時の時価によって算定されます。
生前贈与と相続の関係についての問題は弁護士にご相談ください
今回は、どのような生前贈与が特別受益にあたるのかを紹介してきました。特別受益があるかないかで、遺産の分け方は大きく変わります。そのため、生前贈与を受けた相続人と贈与を受けていない他の相続人との間でもめてしまう原因にもなります。
生前贈与が、特別受益にあたるかどうかを判断するためには、法律的な知識を必要とし、それぞれの生前贈与の状況に応じて個別に判断することになります。また、生前贈与を受けたのがかなり前の場合には、相続開始時にその評価額が変動している可能性もあります。
不動産を生前贈与された場合には、相続開始時のその評価額の算出は複雑になるため、個人で調べていくことには限界もあると思います。また、状況によっては、生前贈与を受けた際の状態と相続開始時の贈与されたものの形式が変更されていたり、無くなっていたりするケースもあり得ます。そのため、このような様々な生前贈与に関する相続問題については、相続に詳しい弁護士へ相談いただき、解決をしていくことをおすすめします。
弁護士は、その生前贈与が特別受益にあたるのかどうかを判断し、適切なアドバイスをすることができます。また、生前贈与が原因で相続人同士の争いが起きている、起きそうな場合にも、依頼者様の代理人として法律に基づいてしっかりと交渉を行い、依頼者様の負担を減らすことがきます。
生前贈与が絡む相続問題でお困りの場合には、弁護士法人シーライトにご相談ください。
 弁護士法人シーライト
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は500件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介