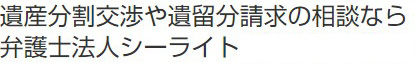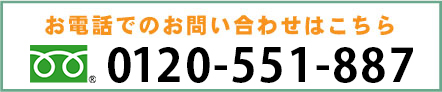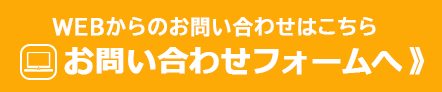遺言としては無効でも死因贈与としては有効になるの?

遺言は、被相続人が自身の死後の遺産分割に関して、意思を明確にするための重要な手段です。ただし、この遺言には厳格な形式のルールがあります。
そのため、少しでもその形式要件が欠けていると無効とされてしまいます。では、被相続人が作成した遺言が無効となってしまった場合、その遺言は何の効力もなくなってしまうのでしょうか。基本的には、遺言が無効となった場合、相続人は、相続財産に対してそれぞれ法定相続分に応じた共有持分を有する状態となります。しかし、状況によっては、遺言としては無効であった場合でも、死因贈与として有効になる可能性があります。
今回は、遺言と死因贈与の基本的な違いや、どのような場合に無効な遺言が死因贈与として効力を持つのか、また相続トラブルが発生した際に弁護士へ相談するべき理由について解説します。
目次
遺言の意義について
遺言は、被相続人が亡くなられた後の自己の財産などに関して、被相続人の意思を可能な限り尊重するための文書であり、被相続人の最終の意思表示になります。遺言が有効であれば、相続の方法や分配についての基準は、その内容に従うことが原則となります。そのため、法定相続人以外の人に財産を残すことなども可能です。
しかし、冒頭でも説明したように、遺言には厳格な形式のルールが求められています。もし、そのルール通りに作成されていない場合には、せっかく作成した遺言も無効となってしまいます。
遺言が無効となる場合について
遺言が無効となる基準は、遺言の種類によって異なります。
遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。
普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式の遺言には、①一般危急時遺言、②難船危急時遺言、③一般隔絶地遺言、④船舶隔絶地遺言の4つがあります。
今回は、自筆証書遺言についてのみご紹介します。
自筆証書遺言が無効になるケースについて
1.形式不備
遺言が法律で定められた方式を充たしていない場合、無効とされます。
たとえば、自筆証書遺言では、全文が遺言者の自筆であることや署名や押印、遺言書の作成年月日が入っていることなどが形式の要件として挙げられます。
2.遺言者の意思能力の欠如
遺言作成時に遺言者が意思能力(判断能力)を欠いていた場合、無効とされる可能性があります。
たとえば、高齢で認知症を患っている場合や遺言者が15歳未満だった場合などが該当します。
3.遺言の内容が不明確
遺言の内容が理解しづらい場合には、内容が理解できない部分について効力が生じない可能性があります。
たとえば、複数土地を所有し、子どもも一人ではない被相続人が、遺言書に「土地を子どもに譲る」とだけ記載していた場合に、どの土地をどの子どもに相続させるのかが不明確であるため効力が生じないと考えられます。
4.詐欺や強迫があった場合
第三者の影響で遺言者が自由な意思で遺言を作成できなかった場合も無効となる可能性があります。
5.公序良俗違反
遺言内容が法律や社会的秩序に反する場合、無効となる場合があります。
以上1~5のような場合などには、遺言が無効となる可能性があります。また、ここに記載した無効となる基準については、一部の例となります。
普通方式の遺言が無効になってしまうケースについては、こちらのコラムで詳しく紹介しています
死因贈与とは?
死因贈与は、民法第554条に規定されている贈与契約の一種になります。これは、被相続人が死亡した時点で財産を譲渡する契約です。
契約という形を取るため、贈与者(財産を与える側)と受贈者(財産を受け取る側)の合意により契約が成立します。遺言のように厳格な要式性はなく、契約書がなくても死因贈与契約は成立します。この点について、最高裁判所昭和32年5月21日判決で、「民法554条の規定は、死因贈与の効力については遺贈に関する規定に従うべきことを規定しただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定に従うべきことを定めたものではない」と判断しています。
しかし、契約書がないと死因贈与契約を立証しにくいため、契約書等を作成しておくと良いでしょう。他にも、自宅などの不動産を贈与する場合には、死因贈与契約書を公正証書で作成し、受贈者を執行者とする旨を記載しておけば、登記をする際の負担を減らすことができます。
遺言と死因贈与の違い
遺言と死因贈与の違いについてまとめます。
法的性質
遺言については、法的に有効な遺言であれば、相続人が遺言の内容を開示されるまで内容を知らない場合でも、当事者間の合意は必要なく、単独行為として一方的に行うことができます。
一方、死因贈与については、当事者間の合意によって成立する契約であるため、内容について双方が合意していなければ成立しません。
財産の処理についてできる範囲
死因贈与は財産の贈与に関することのみしか契約できません。これに対し遺言は、財産の分配の他に生命保険金の受取人の変更などもすることができます。
方式
遺言には厳格な方式がありますが、死因贈与には特に厳格な方式は設けられていません。そのため、死因贈与契約は、口頭契約でも成立する場合がありますが、書面によって合意を明確にすることで、贈与契約の存在を証明しやすくなります。
無効な遺言が死因贈与として有効とされるケース
遺言が形式不備で無効となった場合でも、その内容について受け取る側も把握している場合などには、死因贈与として効力を持つ可能性があります。実際に、無効となってしまった遺言が死因贈与として有効とされた裁判例がいくつか存在しますので、ご紹介します。
自筆証書遺言に押印がなかったため、様式性を欠き遺言としては無効になってしまった事例です。
しかし、遺言の記載内容全体から死因贈与の申込みに意思表示がなされたと理解できること、遺言の作成時点で受贈者も贈与の申込みを受諾したと認められることから、遺言の死因贈与への転換を認めました。
作成日付の記載を欠く自筆証書遺言について無効となってしまった事例となります。
被相続人の生前に献身的に身の回りの世話をしてくれた女性に対し、遺産の一部を贈与しようと考え、手紙を自筆で作成し、署名捺印をして女性に手渡したケースですが、自筆証書遺言としての様式性を欠いていたため、無効とされました。しかし、女性が、手紙を受け取り、贈与を受け入れていたことなどから、死因贈与として有効と判断されました。
被相続人本人が自筆で作成せず、別の人間が被相続人の話した内容を書き写したために、無効となった事例です。
被相続人が入院中に口頭で話した内容を弟が書き写し、本人が署名押印しました。遺言の内容は、「死後自己所有の財産を、養子であるXを除外して、実子であるYらに取得させる」という内容でした。そのため、相続人Xは、「遺言書としては無効」として、遺言の有効性を争ったケースとなります。
これに対し、裁判所は「被相続人が、本件遺言書の作成当日に弟を介して、受贈者であるYらにその内容を開示していること等の点で、遺言書は死因贈与の意思表示を含むものと認められる」と判断して、死因贈与の効果を認めました。
無効な遺言の死因贈与への転換を認めなかったケース
被相続人が公正証書遺言を遺したものの、証人が欠格者になっていたために、遺言としては無効であった事例です。
被相続人は、子どもに土地などを遺贈する旨を公正証書遺言に記載していたものの、子ども本人は、遺言の存在を父親の死後に初めて知ったという事情があり、裁判所は、死因贈与の意思表示の合致を認めず、無効な公正証書遺言について死因贈与の転換も認められないと判断しました。
被相続人の友人が代書で作成した遺言であったために無効となった事例です。
被相続人は、「全ての財産を孫に残す」という旨の遺言を作成しましたが、友人は、この遺言を、被相続人の葬儀の日まで保管しており、孫は葬儀の日以前に遺言を見る機会はなかったとして、被相続人の死因贈与の意思表示とは認められず、孫側における承諾も認められないとして、死因贈与への転換を否定しました。
無効な遺言書の死因贈与への転換認定要素
死因贈与は契約のため、贈与者側の「死因贈与の意思」と受贈者側の「贈与を受ける意思」が合致していることが必要となります。無効となってしまった遺言が、死因贈与へ転換を認められるためには以下の要素が必要となります。
1.贈与者に死因贈与の意思が明確にあること
2.受贈者が贈与者の意思を認識し合意があること
3.合意の証拠(書面、証言、行動など)が存在すること
さらに書面作成の経緯や保管状況、遺言者と受贈者の生前のやり取り、受贈者以外の親族の認識など各種の事情も考慮され、総合的に判断されます。
相続に詳しい弁護士に依頼するメリット
遺言や死因贈与に関する問題は法律が絡むため、相続に関する法律を熟知していない人が対応していくには限界があります。相続に詳しい弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
専門的な法律判断が可能
弁護士は、遺言の有効性や死因贈与契約の成立要件について、専門的な知識を持っています。これにより、遺言や死因贈与がどのように解釈されるべきかを適切に判断できます。
相続トラブルの迅速な解決
弁護士は、無効な遺言により発生する遺産分割協議や死因贈与契約をめぐる争いが発生してしまった場合にも、法的な見解に基づき冷静かつ迅速に解決策を提案します。
証拠の整理と交渉力
遺言が無効となってしまい、死因贈与契約の成立を証明するためには、法的な証拠が必要となります。相続に詳しい弁護士は、死因贈与契約の成立を証明するための証拠の収集や整理を行い、必要に応じて裁判所での主張を効果的に行います。
相続問題でお困りの場合は弁護士法人シーライトにご相談ください
無効な遺言であっても、状況によっては死因贈与として転換を認められる場合があります。しかし、それを法的に認めてもらうには多くの要素を満たし、適切な証拠を揃える必要があります。このような作業を個人で行っていくのは、非常に大変な作業となります。
遺言や死因贈与に関する問題を抱えている場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。弁護士法人シーライトでは、依頼者の方の立場を守り、相続に関するトラブルを回避しつつ、最善の解決策を提案いたします。
 弁護士法人シーライト
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は500件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介