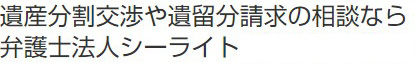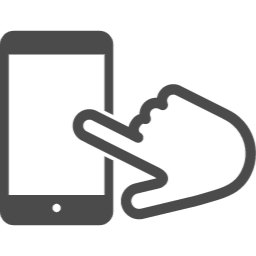遺留分侵害額請求したいが、遺産に借金が含まれている場合、債務も取得することになるのか?

相続が開始され、被相続人が遺した遺言に「〇〇にすべての財産を相続させる」といった旨が記載されており、財産を取得できない他の相続人は、遺留分を請求しようと検討している場合、相続財産の中に負債もあるときには、遺留分侵害額請求をするとその債務も負う必要があるのかどうか気になるところだと思います。
今回は、遺産に借金などの負債が含まれている場合、遺留分侵害額がどうのように評価されるのかについて解説します。
目次
共同相続人の間での債務承継の割合について
相続財産に可分債務(※1)があり相続人が複数人いる場合、相続を放棄しない限り、法定相続分に従って債務を負担するか、相続分が指定(または包括遺贈※2)されていた場合には、指定相続分によって債務を負担することになります。
指定相続分による債務負担とは、被相続人が、遺言で各相続人の積極財産(預貯金や不動産など、経済的に価値があると認められるものをいいます。)の相続分を指定している場合には、消極財産(借金などの債務)も同じ割合で負担することです。
もし、遺言の定めがなければ遺産分割協議によって、相続債務の承継者や承継割合を定めることもできます。
※1可分債務とは、1個の分割可能な債務に多数の債務者が存在している債務のことです。
※2包括遺贈とは、特定の相続財産を遺贈するのではなく、相続財産の割合を指定して財産を遺すことをいいます。
しかし、この相続分の指定や遺産分割協議で決まった承継割合は、債権者との関係において扱いが異なります。
相続債権者に対する効力について
たとえ遺言によって、法定相続分とは異なる相続分が指定されたとしても、被相続人の債権者がその遺言の内容を知っているかどうかは分かりません。
遺言によって、法定相続分とは異なる相続分が指定されたケースにおける相続債務の取り扱いについては、債権者は遺言による相続分の指定にかかわらず、法定相続分に従い、各相続人に対して債務の支払いを請求できると最高裁平成21年3月24日判決が規範を示しています。
つまり、相続債権者に対しては、遺言による相続債務についての相続分の指定は効力が及ばないとしています。そのため、たとえ遺言によって別の相続人が相続債務を承継したとしても、それを理由として、債権者からの法定相続分に従った弁済請求を受けてしまった場合、拒否することができません。
しかし、相続債権者が、相続債務についての相続分の指定の効力を承認する場合には、遺言による相続分の指定通りの債務を各相続人は負うことになります。
では、具体例を使って解説したいと思います。
被相続人は、知人のXから生前に1000万円の借金をしていました。遺言では、配偶者Aに全ての遺産を相続させる旨が記載されています。相続を放棄する人は誰もいませんでした。
この例では、遺言によって配偶者Aが全ての遺産を相続することが決定しています。
しかし、知人Xは、遺言による相続分の指定があったとしても、相続人である3人に対して、それぞれ法定相続分に従って債務の履行を請求することができます。
たとえば、配偶者Aに対しては、法定相続分1/2にあたる500万円、2人の子どもに対しては、それぞれに法定相続分1/4である250万円の支払いを請求することが可能です。しかし、実際の相続人間での債務の相続分は配偶者Aが1,000万円、子ども2人は、0円です。そのため、長男も次男も知人Xの請求に応じて債務を支払った場合に、その金額をAに対して請求(求償)できます。もちろん、知人Xが、遺言による相続分の指定を承認して、全ての遺産を相続した配偶者Aに対して1,000万円を支払うように請求することも可能です。
遺留分の計算において被相続人の負債はどのように扱われるのか
遺留分は、特定の相続人が相続することができる最低限の遺産の取り分になります。まずご自身の遺留分がどのくらいなのかを算定するためには、基礎となる財産の価額を求めることが必要です。この遺留分を算定するための財産の価額は、下記のように求めます。
相続開始時における被相続人の積極財産の額(遺贈財産も含まれます)に、第三者への原則相続開始前1年以内の生前贈与や相続人に対する原則相続開始前10年以内の生前贈与を足し、被相続人の負債額を引いたものが遺留分の基礎となる財産合計額となります。
この遺留分の基礎となる財産合計に個別の遺留分割合を乗じたものが遺留分額となります。
ちなみに、生前贈与については、遺留分を計算する際に全ての生前贈与が対象となるわけではありません。
どのような生前贈与が遺留分を侵害してしまう可能性があるかについては、下記の記事で詳しく紹介しています。
では、遺留分の基礎となる財産合計から控除される債務とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
遺留分の基礎となる財産合計から控除される債務の範囲について
被相続人の負担した債務を意味しています。
たとえば、事業や不動産購入などにおいて、銀行や個人などから借金をしていた場合の借入金や被相続人が未払いの家賃や治療費などは、相続人がその債務を負担することになるため、遺留分の算定において、控除される債務となります。
また、公法上の債務も控除される債務となります。たとえば、固定資産税・住民税・所得税などの税金の未納分や罰金の未支払い分についても、被相続人に代わって相続人がこれらを支払わなければなりません。そのため、債務として控除の対象となります。
被相続人が連帯保証人として、連帯保証契約をしていた場合の保証債務については、原則として、債務として控除の対象となりません。
なぜなら、保証債務については、債務を履行した場合は求償権の行使により返還されるという性質を有するため、確実な債務とはいえず、また、保証人が複数人存在するケースもあるため、債務として解する必然性がないからです。
しかし、例外として、保証債務の履行が確実で、かつ、求償権により返還されないことが明らかな場合は債務として控除の対象となります。また、相続財産に関する費用、遺言執行に関する費用、相続税、葬儀費用についても、遺留分算定において控除される債務にはなりません。
遺留分侵害額の算定について
では、相続財産の中に債務が含まれている場合に、侵害されている遺留分の部分について請求するとなった場合どのような計算をしていくのかをご紹介します。
遺留分侵害額とは、遺留分権利者が被相続人の財産から遺留分に相当する財産を受け取ることができない場合の不足額をいいます。
算定方法は下記のようになっています。
=遺留分(遺留分の基礎となる財産合計 × 個別の遺留分割合 )※1
-遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額
-遺産分割の対象財産がある場合、遺留分権利者の具体的相続分に相当する額
+遺留分権利者が負担する債務(これを遺留分権利者承継債務といいます)
※1遺留分の計算方法については、まず遺留分を算定するための財産合計額を算出し、その財産合計額に、個別の遺留分割合を乗じたものです。
遺留分の基礎となる財産合計の式は下記のようになります。
=相続開始時点で被相続人が有したプラスの財産価額
+被相続人が相続開始前に贈与した財産の価額(※2)
-被相続人のマイナスの財産(負債)
※2相続人に対する生前贈与の場合には、原則、相続開始前10年以内に行われたものであること。
また、第三者に対する生前贈与の場合には、原則、相続開始前1年以内のものであること。
遺留分侵害額請求をする場合の生前贈与については、下記の記事で詳しく解説しています。
ここで注意すべきなのは、遺留分権利者が相続によって負担するべき債務の額を加算するという点です。
この遺留分権利者が相続によって負担するべき債務というのは、遺留分の算定方法で説明した被相続人の債務の中から個々の遺留分権利者が負担する債務を指しています。
遺留分侵害額の具体的な計算例の紹介
ここからは、被相続人に負債があった場合の遺留分侵害額の計算例をいくつかご紹介します。
被相続人の財産は、積極財産が6,900万円で、金融機関からの借金3,000万円でした。また、被相続人は、知人Dに対して相続が開始される半年前に4,800万円の生前贈与をしていました。
この場合、子ども3人の遺留分侵害額がいくらになるのかを考えます。
遺留分の箇所で前述した通りの方法で計算します。
積極財産6,900万円+加算されるべき生前贈与4,800万円―債務3,000万円=8,700万円
【手順2】長男A・長女B・次女Cの子ども3人の各遺留分額を計算します。
8,700万円×1/2(相続財産における遺留分の合計割合)÷3(子供の人数)=1,450万円
【手順3】遺留分侵害額の算定をします。
まず、長男A・長女B・次女Cが相続によって取得した財産額を算出します。
6,900万円÷3(法定相続分:子どもの人数)=2,300万円
次に長男A・長女B・次女Cの債務の分担額を計算します。
3,000万円÷3(法定相続分:子どもの人数)=1,000万円
最後に子どもそれぞれの遺留分侵害額を計算します。
1,450万円(遺留分額)-2,300万円(相続によって取得した財産額)+1,000万円(債務の分担額)=150万円
子ども1人あたりの遺留分額が1,450万円で、相続により取得した財産が2,300万円の場合、遺留分額よりも取得した財産の方が上回っているため、遺留分侵害額請求をできないのではないかと思うかもしれません。
しかし、「遺留分権利者が負担すべき相続債務の額」というものあります。法定相続分に従って、それぞれが債務も相続しているため、3,000万円÷3=1,000万円ずつ債務を負担することとなります。この債務の額も加算することにより、150万円を遺留分として請求することができます。
ただし、1,000万円の債務は負担するので、これについては支払わなければなりません。
被相続人は、知人に対して、全財産の半分を包括遺贈する旨の遺言を遺していました。
この場合、子どもAとBの遺留分侵害額はどうなるのでしょうか。
積極財産2,000万円-債務800万円=1,200万円
知人は、包括受遺者となり、取得する額は、積極財産の半分にあたる1,000万円と債務の半分にあたる400万円です。合わせると合計は、600万円(1,000万円-400万円)となります。
【手順2】子どもAとBの各遺留分額を計算します。
1,200万円(遺留分を算定するための基礎となる財産合計)×1/2(相続財産における遺留分の合計割合)÷2(子どもの人数)=300万円
【手順3】遺留分侵害額の算定をします。
子どもAとBが相続によって取得する額は、1,000万円(知人への遺贈後の積極財産額)×1/2(子どもの法定相続分)=500万円
次に、子どもそれぞれの債務の負担額を計算します。
400万円×1/2=200万円
最後に子どもAとBの遺留分侵害額を出します。
300万円―500万円+200万円=0円
この場合の設例では、侵害されている遺留分はないということになり、請求はできません。
債務がある被相続人が相続人の1人に対して全財産を相続させる旨の遺言を遺していた場合、遺留分侵害額請求の算定はどうなるのか?
もし、相続人の1人に全財産を相続させる旨の遺言がされた場合には、被相続人が生前に負った債務についても、当該相続人に相続債務を相続させる意思があったと考えるべきでしょう。
そのため、遺留分権利者の遺留分侵害額を計算するうえで、法定相続分に応じた相続債務の額は加算することはできません。それは、つまり、遺留分権利者が負担する債務は、ゼロということです。
ただし、「相続債権者に対する効力について」の箇所でもふれたように、遺言による相続分の指定があった場合でも、債権者は各相続人に対し、各相続人の法定相続分に従った相続債務の履行を求めることが可能です。
相続に債務があるが、遺留分侵害額請求をしたいと検討されている場合は、弁護士にご相談ください
被相続人が亡くなられて、相続に直面すると、預貯金や土地などの積極財産だけではなく、被相続人の債務(消極財産)も相続しなければならないことがあります。
もし、遺言によって遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を検討することがあるかもしれません。しかし、相続に債務が含まれているケースでは、法律の知識が必要となるため、法律を熟知している弁護士に依頼することをおすすめします。
相続時に遺産と債務がある場合には、それぞれを正確に評価するために詳細な財産調査が必要になりますが、ご自身だけで調査を進めることは大変なことです。弁護士は、このような調査を専門的に行い、依頼者の方に適切なアドバイスをすることができます。
いざ、遺留分侵害額請求を行うとなった場合には、相続人が自身で請求をすることも可能ですが、遺産に債務が含まれているときの遺留分侵害額請求の算定は、複雑な計算をすることが多いため、債務が誰にどのように分配されるのか、遺留分侵害額はどうなるのかなどを正確に判断するためには、法律の専門知識が必要となります。
また、遺留分侵害額請求は、法的な手続が伴います。請求のための書面作成や遺留分侵害をしている相手方との交渉、場合によっては訴訟手続が必要になることもあり、これらをご自身で行うのは負担が大きく、希望されている結果にならない場合もあります。
相続は、相続人同士の感情的なぶつかり合いから争いに発展するケースもあります。弁護士は、ご依頼者の方の代理人として争いがある相手との間に入り、冷静かつ公正な視点で調整を進めることができ、有利な結果を得る可能性が高まります。
以上のような複雑な手続や相手方とのやり取りを弁護士に任せることで、ご自身の負担を大幅に軽減することができます。特に、感情的になりやすい相続問題においては、弁護士が代わりに対応することで、精神的なストレス軽減につながるかと思います。
もし相続に関する不安や疑問がある場合は、当事務所にご相談ください。
 弁護士法人シーライト
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は500件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介