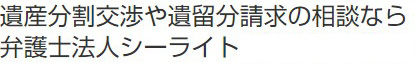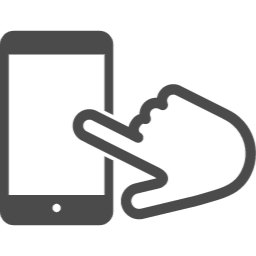生命保険での遺留分対策について解説

生命保険金は、保険金受取人の固有の財産となるため原則として相続財産とはなりません。そのため、相続対策のうち遺留分対策として生命保険金を活用するのは有効な手段となります。ただし、生命保険金は、原則として相続財産ではないとされていても、遺産額に対して6割を超えてくる保険金額に対しては、特別受益として遺産への持ち戻しを行い、遺留分の対象となる可能性があります。今回は、生命保険と遺留分の関係について解説し、遺留分対策としての活用方法についても説明いたします。
目次
生命保険と遺留分の関係について
前述したように、例外的に生命保険金が遺留分の対象になる場合もあります。そのため、生命保険金が遺留分の対象になった場合には、遺留分の金額が増えるため、相続人同士のトラブルに発展することもあります。そのような生命保険金をめぐる相続トラブルを防ぐためにも、遺留分について理解しておくことが大切です。
遺留分について
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の遺産の取分のことです。この遺留分は、法定相続人の正当な権利であり、遺言よりも優先されるものとなっています。遺言の内容によっては、一部の相続人が受け取る財産が、保障されている遺留分に満たないこともあります。その結果、その遺言の内容に不満を感じている相続人は、遺留分侵害額請求権をすることで、その相続人の遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。また、遺留分には割合があり、請求できる割合が決められています。
生命保険は、原則として遺留分の対象にはならない
生命保険金が相続財産であるかどうか争われた事案において、最高裁昭和40年2月2日判決では、「生命保険金は、保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであって、保険契約又は被保険者から承継して取得するものではない」として、生命保険金が、相続財産ではなく生命保険金受取人の固有財産であると判断しました。また、生命保険金の請求権は被保険者が死亡したときに初めて発生するものなので、被相続人から受取人へ遺贈や生前贈与されたものと考えることもできません。したがって、生命保険金は、遺留分の基礎財産となるものではないということになります。そのため保険金の受取人は、保険金を満額受け取ることができます。
遺留分の基礎となる財産は、相続開始時の被相続人の財産と生前に贈与された財産になります。ちなみに、生前に贈与された財産は、相続人ではない人への贈与であれば、相続開始前1年間に贈与されたものが遺留分の対象となります。相続人に対する贈与が特別受益に当たる場合には、相続開始前10年間に贈与されたものが遺留分の対象となります。また、当事者双方が遺留分を侵害すると知って行われた贈与は期間の制限なく遺留分の対象です。
生命保険金の受取人の変更は、遺留分の対象となるのか
被相続人が生前に、生命保険の受取人を変更することや遺言により生命保険の受取人を変更することがあります。そのような場合には、相続人の取り分に影響を及ぼすこともあります。では、生命保険金の受取人の変更は、遺贈または贈与にあたるのでしょうか。この受取人の変更についても裁判例をご紹介します。被相続人が当初妻を受取人とする生命保険をかけていたところ、受取人を相続人以外の第三者に変更した事例で、最高裁平成14年11月5日判決(民集56巻8号2069頁)は、遺留分減殺請求の対象にはならないと判断しました。したがって、生命保険金の受取人を変更することも、遺留分の対象にはなりません。
生命保険が遺留分の対象になる場合について
では、生命保険は、相続財産でないため遺留分対策として有効な手段であるからといって、被相続人の金融資産を生命保険に変更して高額な契約をすることは正解なのでしょうか。この点については、正しい部分もあるけれど不正確といえるでしょう。正確には、生命保険金は、原則として、遺留分侵害額請求権の対象にはなりません。しかし、この原則を貫くと相続人の間で著しい不公平が生じることもあります。そのような場合には例外として、生命保険金が相続財産に持ち戻されることがあります。その結果、相続財産が増加することで、遺留分も増加することになります。これについては、相続人が保険金受取人として取得する死亡保険金請求権または、取得した死亡保険金が民法第903条1項の特別受益に規定する遺贈または贈与にかかる財産にあたるかどうかが争われた事案があります。
最高裁平成16年10月29日の判決では、特別受益に該当する遺贈または贈与にかかる財産にはあたらないと判断したうえで、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となるとしました。つまり、相続人の間で著しい不公平が生じる場合、生命保険金請求権が持ち戻しの対象になれば、生命保険金がみなし相続財産となり、遺留分の計算の基礎となる財産が増加するため、遺留分侵害額も増加するということになります。そうなると、生命保険は、遺留分対策として必ずしも万全であるとはいえないということになります。では、生命保険が遺留分の基礎財産となる条件とは何なのでしょうか。
生命保険が遺留分の基礎財産となる条件について
このことについて最高裁の判例では、以下のような諸事情を総合的に考慮して、相続人間に著しい不公平が生じているといえるかどうかを判断すべきとしています。
生命保険金の額
遺産総額と生命保険金の額との比率
受取人が被相続人と同居していたか否か
受取人が介護等によって被相続人の財産の形成・維持に貢献していた度合い
その他、受取人と他の相続人との関係
各相続人の生活の実態など
最高裁の判例や裁判例では、生命保険金額の遺産に対する割合が6割を超えてくると、特別受益となることが認められやすい傾向にあります。
生命保険が持ち戻しの対象となる具体例
たとえば、
相続人が長男と長女の2人の子どもで、被相続人の遺産総額は2,000万円、生命保険金が1億円という状況があったとします。
被相続人の遺言書には、1億円の生命保険金は長男が受け取り、2,000万円の預金は、長男と長女に半分ずつ相続させると書かれてあったとします。
このような場合、生命保険金が遺留分の対象にならないとすれば、長女は1,000万円を相続するため遺留分を主張できるに過ぎません。
なぜなら、この場合の遺留分は、2,000万円の1/4にあたる500万円であり、長女は遺留分以上の財産を相続することになるため遺留分は発生しないためです。そうなると、長男は、生命保険金1億円と被相続人の預金1,000万円を相続し、長女は、被相続人の預金1,000万円のみ相続するという著しい不公平が生じています。このケースでは、生命保険金1億円という金額は、遺産総額2,000万円に対して大きな比率を占めています。生命保険金の受取人である長男が、被相続人の財産形成に大きく貢献していたなどの特別な事情がない限りは、判例によれば生命保険金が遺留分算定の基礎となる財産に含まれる可能性が高いと考えられます。
もし生命保険金が遺留分の対象になると判断されると、生命保険金の1億円が相続財産に持ち戻され、みなし相続財産は1億2,000万円となります。長女は、この1億2,000万円の1/4に相当する3,000万円から長女の相続分1,000万円を差し引いた2,000万円について遺留分を主張できることになります。
生命保険金の特別受益該当性を否定した新たな裁判例
生命保険金がかなり高額で、保険金が遺産に占める割合が6割を超えるような場合には、特別受益と判断されることがあると説明しましたが、広島高等裁判所令和4年2月25日の決定では、異色の決定が下りました。
生命保険金が遺産に占める割合がかなり大きかったのにも関わらず、特別受益を否定する新たな裁判例が出ました。これは、被相続人の母親と被相続人の配偶者である妻が法定相続人となった事案になります。
相続開始時の遺産の評価額は約770万円で、妻が死亡保険金2,100万円を受け取ったことで、被相続人の母親が、死亡保険金は特別受益に該当すると主張しました。しかし、広島高等裁判所は、生命保険金が遺産の2.7倍の事案に対して特別受益を否定する判断をしました。裁判例は下記のとおりの指摘をしています。
公益財団法人Dの生活保障に関する平成28年度速報版の調査によると、男性加入者が病気によって死亡した際に民間生命保険により支払われる生命保険金額の平均は、平成3年で2,647万円、平成28年で1,850万円であったという事実を認定しそのうえで裁判所が考えている考慮要素を次のように説明しました。
① 死亡保険金の額は、一般的な夫婦における夫を被保険者とする生命保険金の額と比較して、さほど高額なものとはいえないという点。
② 被相続人と妻は、婚姻期間約20年、婚姻前を含めた同居期間約30年の夫婦であり、その間、妻は一貫して専業主婦で、子どもがなく、被相続人の収入以外に収入を得る手段を得ていなかった点。
③ 生命保険は、妻との婚姻を機に死亡保険金の受取人が妻に変更されるとともに死亡保険金の金額を減額変更し、被相続人の手取り月額の給与から保険料として過大ではない14,000円を毎月払い込んでいた点。
④ 妻は現在54歳の借家住まいであり、本件死亡保険金により生活を保障すべき期間が相当長期間にわたることが見込まれる点。
⑤ 母親は、被相続人と長年別居し、生計を別にする母親であり、夫の遺産であった不動産に長女及び二女と共に暮らしている点。
以上から、保険金受取人である被相続人の配偶者と被相続人の母親との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がないと判断されました。
このように必ずしも、生命保険金の遺産に占める割合が多いからといって、持ち戻しの対象となるわけではなく様々な点を考慮して判断されるということになります。しかし、ご自身でこの生命保険が果たして遺留分の対象となるかどうか判断するのは非常に難しい問題といえます。そのため、相続に詳しい弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
生命保険を活用した相続対策の例
今までは、生命保険が遺留分の対象となるかという点について説明してきましたが、少し違う角度から生命保険を相続対策として活用する例をご紹介します。
A氏は、再婚しており現在の配偶者との間に子どもはなく、離婚した前の配偶者との間に子どもが1人いました。A氏の主な財産が自宅と土地建物のため、現在の配偶者にこの財産を残したいけれど、前の配偶者が引きとった子どもが遺留分を主張してきたら、現金も少ないためどうしようかと悩んでいました。
そこで、遺言書に現在の配偶者に遺産の全部を相続させるという遺言を作成し、その際に前の配偶者との子どもが遺留分を請求してきた場合の対策として、A氏が、現在の配偶者を受取人とする終身生命保険に加入し、その死亡保険金を前の配偶者との子どもの遺留分対策資金にあてることで遺留分対策をするというものです。
生命保険の適切な活用を考える
生命保険は、遺留分対策として万全ではないと説明しましたが、生前に行える相続対策として有用であることに変わりはありません。ただし、前述したように、相続財産と比較して、度を越した生命保険の加入はかえって遺留分の問題を引き起こすことになりかねません。それが結果として、相続人同士のトラブルに発展してしまうことがあることに留意する必要があります。そこで、将来的な遺せる遺産額を踏まえつつ、適切な金額の生命保険に加入することで有用な遺留分対策を行うと良いかと思います。
生命保険以外にもある遺留分対策について
生命保険金の有無に関係なく、遺産相続は、相続人の間でトラブルに発展しやすいです。相続人同士の仲が良好でない場合や被相続人と特定の相続人が不仲である場合などには、特に相続について争いが起きやすい傾向にあります。ここからは生命保険以外にも遺留分対策として行える方法をご紹介します。
生前贈与を行う
被相続人が生前に、財産を多く渡したい相続人へ贈与することで、将来的な相続財産を減らし、財産を渡したくない相続人の遺留分を減らすことができます。ただし、相続人に対する生前贈与については、相続開始前の10年間にした生前贈与が遺留分の対象となるため、長期計画を立てて生前贈与を行う必要があります。なお、相続人以外の第三者に対しての生前贈与については、相続開始前の1年間にしたものが遺留分を算定するための財産の価額として考慮されることとなります。また、生前贈与は、贈与税の課税対象とはなりますが、非課税措置を利用し、相続時の相続財産の総額を減らすことで、相続税対策としても有効です。相続税は、被相続人の相続財産に応じて課税されます。相続税には、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるので、相続財産の総額が、この基礎控除額を上回る場合には、相続税を納める必要があります。
贈与税の非課税措置について
暦年贈与による相続対策を行う
暦年贈与とは、年間110万円以下であれば贈与税がかからず、贈与税を非課税とする方法のことです。ただし、相続開始前7年間に贈与されたものについては、年間110万円以下でも相続税の課税対象となる点に注意が必要です。以前は、相続開始前3年間とされていましたが、税法の改正により2024年1月から7年間に延長されました。
相続時精算課税を活用した相続対策を行う
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの生前贈与については贈与税を支払わず、贈与者の死亡後に相続税の課税対象として精算できる制度のことです。この制度を利用した場合、税法の改正により、2024年1月からは基礎控除110万円以下の部分は非課税となりました。
他にも下記のような非課税措置があります。
贈与税の配偶者控除(2,000万円まで)
教育資金の贈与税の非課税措置(1,500万円まで)
結婚、子育て資金の贈与税の非課税措置(1,000万円まで)
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(1,000万円または500万円まで)
特定障害者等に対する贈与税の非課税制度(6,000万円または3,000万円まで)
遺留分の放棄
遺留分に関する相続人同士のトラブルが気になる場合には、事前に遺留分を放棄してもらうことも検討しましょう。遺留分の放棄とは、相続人が自らの意思で遺留分権を放棄することをいいます。遺留分の放棄は、相続の放棄とは異なるため、相続人となることに変わりはありません。被相続人の生前に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所による許可を得る必要があります。家庭裁判所の許可が必要なのは、被相続人や他の共同相続人らによる不当な働きかけを防止するためです。家庭裁判所で、遺留分の放棄をする相続人の自由意思、放棄理由の合理性や必要性、放棄と引き換えの代償の有無などを考慮して判断されるため、必ず遺留分の放棄が許可されるわけではありません。
遺留分の放棄は、相続人自身が行うものであり、当然当該相続人が納得してくれるような条件を提示しなくてはなりません。たとえば、被相続人が自宅で家業営んでおり、それを長男に継いでほしいので、長男に対して相続財産である不動産を渡したいけれどが、他の子どもの遺留分を侵害してしまう場合は、他の子どもを生命保険金の受取人に指定する代わりに、遺留分を放棄してもらうという方法があります。
遺留分に関する問題は弁護士にご相談ください
遺留分を含め相続の問題は、誰にでも起こり得る問題です。適切に相続対策をすることで相続人同士のトラブルを防止することができます。生命保険金の活用を含め、相続対策をお考えの方は、弁護士にご相談ください。弁護士のサポート受けることで、様々なメリットを得ることができます。
生命保険金が遺留分の対象になるかどうかについて適切なアドバイスが受けられます。もし、生命保険金が遺留分の対象になる可能性がある場合には、生前贈与や遺留分の放棄など、ご相談者様の状況に応じた対策を弁護士が提案することができます。生命保険金を受け取ったことで、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合にも、弁護士に対応を任せることができます。他の相続人とのやり取りを弁護士に一任できることでご自身の負担を減らすことができます。また、相続人同士が話し合うと感情的になってしまうことも多いですが、弁護士が代理人として相手側と交渉することで冷静な話し合いが可能になります。遺留分の請求額があまりにも過大な場合には、弁護士が正当な主張をし、交渉をすることで適切な条件での解決を目指すことができます。
もし、相手方との話し合いが成立しないとき、調停や訴訟手続に進んだ場合でも、弁護士に依頼することで複雑な手続を一任できます。生命保険による遺留分に関する問題についてお困りの場合には、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。弁護士法人シーライトでは、遺留分に関するご相談も受け付けております。
 弁護士法人シーライト
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は500件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介