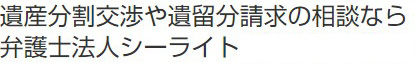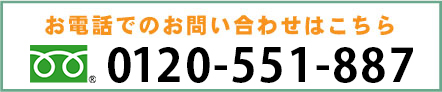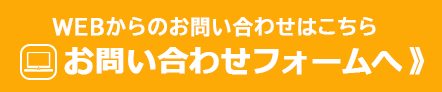共同相続した不動産の共有状態を解消したい場合はどうしたらいいのか?~共有物分割請求について~

不動産を持っていた人が亡くなった場合、法定相続人が、その不動産について遺産分割協議をしないまま共有にしている状態を遺産共有といいます。相続財産の中に不動産があることはよくあるケースですが、その不動産を共有とすることは、あまりおすすめできません。
なぜなら、不動産の共有関係が生じたとしても、共有者全員が仲良く不動産を利用できている状態であれば、問題は起きづらいといえますが、共有者の一部の人が不動産を使用し、他の共有者には使用の対価等も支払われていないような状況の場合には、共有者間において対立関係が生じるケースなどがあるからです。不動産を共同相続している状態ではあるけれど、その共有状態を解消したいと考えている場合には、法的な方法や手続が必要となります。
今回は、不動産共有により起こるデメリットや不動産の共有状態の解消方法などについてご紹介します。
目次
相続した不動産の遺産分割
遺産に不動産が含まれている場合の分割方法には、いくつかの分割方法があります。現物分割、代償分割、換価分割、共有分割になります。
現物分割
たとえば不動産は長男、預貯金は長女など財産をそのままの形で各相続人が相続する方法になります。
もし、不動産しか遺産と呼べるものがない場合、不動産を物理的に分割する方法となります。たとえば、土地を分ける場合、1つの土地を分筆した上で、相続人がそれぞれ、分筆後の土地を取得することになります。
代償分割
主な遺産が不動産しかない場合、たとえば長男がその不動産を相続する代わりに長男から不動産を取得しない他の法定相続人へ相当額の対価を支払うなど、金銭のやり取りで調整して相続する方法になります。
換価分割
遺産である不動産を売却した対価を相続人で分割し相続する方法になります。
共有分割
不動産を複数人の相続人共同で所有している状態になります。
遺産の内訳や事情によっては、採用できない分割方法もあります。たとえば、相続人の1人である長男が配偶者と共に、被相続人の生前から被相続人の家に一緒に住んでいた場合を考えてみます。
被相続人の主な遺産が、その住んでいた不動産であり、突然の他界で、特に遺言も残されていない場合には、被相続人の所有していた不動産をどのように分割するか相続人同士で決める必要があります。
長男一家は、被相続人の生前から同居をしており、すでにその土地に生活基盤ができている場合には、換価分割は現実的ではないでしょう。また、現物分割をするにしても、そこまで大きな土地でない場合には難しい可能性もあります。そうであるからといって代償分割をしようにも、長男が、他の相続人へ代償金を支払えるだけのお金がなければ、この方法の選択も困難です。
このように他の方法が取れない場合に、やむを得ず共有分割を選択することがあります。こういった事情から、相続を機に不動産が共有となってしまうケースが少なくありません。
もちろん使用している相続人に対して、共有者は、法律上使用料を請求できますが、そういった法律を知らない場合もあります。そうなると、不動産を使用していない共有者にとってメリットがないため、使用している相続人に共有持分を買い取ってもらいたいと考えるケースも出てきます。
不動産の共有がデメリットとなる理由
では、不動産を共同相続していると、どのような問題が発生するのでしょうか。
1.意思決定が困難になる
共有者は、共有物(全体を対象とする)に関するさまざまな意思決定について、単独で決定ができないことが多いです。具体的な行為によって同意が必要な共有者の数が決まってきます。その具体的な行為とは、共有物の変更(処分)・管理・保存に分類されます。そして、令和3年の民法改正で、軽微変更が加わりました。変更行為のうち軽微なものは管理行為と同じ扱いとするというものです。
以上のように、変更(処分)・管理(軽微変更を含む)・保存のどれに分類されるかによって、意思決定の要件が違ってきます。
変更(処分)の意思決定の要件
変更(処分)の意思決定には、共有者全員の同意が必要となります。
変更(処分)に分類される行為とは、物理的変化を伴う行為、法律的な処分のことです。しかし、実際に、変更(処分)に該当するかどうかは個別的事情で決まるといえるため、はっきりと判定できないことが多いです。
たとえば、不動産に関するさまざまな工事は、小規模なものでない限り、変更の行為に含まれます。土地であれば造成工事やその土地上への建物の建築工事、建物であれば増築や大規模修繕などです。
また、所有権を失う売買(売却)や所有権を失うことにつながる担保権設定は、処分行為にあたります。もし、共有者の一部がこれらを行いたいと考えていても、共有者の中に1人でも反対する人がいれば実行することはできません。
管理(軽微変更を含む)の意思決定の要件
管理行為の意思決定には、共有持分の価格の過半数を有する共有者の同意が必要となります。管理行為に分類される行為については、利用と改良行為があります。
たとえば、共有者のうち誰が使用するかを決めることは、管理行為になります。また、賃貸借契約の締結についても下記(①と②)の両方に該当しない締結の場合は、管理行為となります。
① 短期賃貸借の期間を超えている場合
② 借地借家法の適用がある場合
軽微変更に該当する行為としては、共有私道のアスファルト舗装、植樹伐採、共有建物の大規模修繕、共有土地の分筆と合筆などが挙げられます。しかし、変更(処分)と同様に、実際に該当するかどうかは個別的事情で決まってくるため、はっきりと判定することが難しいです。
保存の意思決定の要件
保存は、各共有者が単独で行うことができる行為のため、意思決定というプロセスが不要です。保存は、物理的な現状を維持し、かつ、他の共有者に不利益が及ばない行為になります。たとえば、路面のアスファルト損傷やL字溝が損傷した時に、損傷箇所だけを修復することは保存行為にあたります。
2.共有者の数が増加する可能性
不動産の共有状態を放置しておくと、その後共有者に相続が発生し共有者の人数が増加してしまい、ますます権利関係が複雑化するおそれがあります。また、共有者の人数が増えれば、合意形成がますます難しくなるでしょう。
たとえば、親が他界し、親の住んでいた不動産を息子2人が共有とした場合を例に考えてみます。
その後息子2人は、それぞれ結婚し、配偶者と子どもとそれぞれの家に住んでいる状況で、息子2人も亡くなり相続が発生すると、今度はそれぞれの配偶者や子どもとの間で共有状態となります。このように代替わりを重ねるごとに関係性の遠い人同士の共有となっていくため、変更や管理の際に意見をまとめることや共有の解消を求めることがさらに困難となっていきます。
3.感情的な対立
共有関係は、しばしば感情的な対立を引き起こす原因にもなります。最初は良好な関係であった場合でも、ささいなことがきっかけで感情的な争いに発展することがあります。
このような問題が不動産の共有状態は発生する可能性が高いため、不動産の共有関係を解消することには、メリットがあります。
共有物分割請求とは
前述したように共有物の変更(処分)や管理に関する意思決定は単独ではできないため、不動産の共有は使い勝手が悪いというデメリットがあります。そこで、すべての共有者には、原則としていつでも共有物の分割を請求できる権利があります。ただし、共有物分割禁止特約が存在する場合には、共有物分割請求が認められません。
共有物分割禁止特約とは、共有者が設定できる特約で、共有物の分割をしたくないとき、その旨を定めることができます。なお、共有物分割禁止特約の期間は上限5年となっており、更新が可能とされています。つまり、各共有者は、共有物分割禁止の合意がある場合を除き、いつでも共有物の分割を請求することができます。
不動産共有状態を解消する方法
不動産の共有状態を解消するには、次のような手順で対応していくことになります。
共有者全員による協議
まずは、共有をしている当事者同士で話合いを行います。共有している不動産を特定の共有者のみが利用している場合には、その共有者に「買い取ってもらえるか」などの提案を行います。もちろん、任意に買い取ってもらう以外の方法で解消することも可能です。
たとえば他にも、無償で共有持分をもらう方法や第三者へ売却して対価を分ける方法など、解消方法は自由になります。
しかし、共有者間の関係性が良くない状況で、土地の利用方法について対立がある場合などには、話合いでまとまらない可能性が高くなります。もし、共有者間での争いがありそうな場合などには、不動産に詳しい弁護士へ相談して、話合いの方向性を決めておくのも1つの方法となります。結果的に共有者同士で合意に至らない場合には、共有物分割請求調停にて解決を目指すことを検討します。
共有物分割請求調停
共有物分割請求調停は、調停委員の立ち合いのもと、家庭裁判所で共有物分割へ向けた話合いをすることです。
第三者である調停委員が立ち会うことで、冷静に話し合いをすすめることができる点や、話し合いで記録された調書は法的な効力を持つため、調停で合意した内容を後から否定されるリスクを減らせる点はメリットになります。
ちなみに、不動産の共有の状態について解決を急いでいる場合や調停に進んでも話し合いがまとまる見込みが低いと考える場合などには、調停ではなく訴訟(裁判)を提起することも可能です。
共有物分割請求訴訟
共有物分割請求訴訟とは、裁判所に共有状態の解消方法を決めてもらうための裁判になります。裁判所は、共有者間にとってもっとも適切と判断した分割方法で共有物を分割します。裁判所の判断により共有状態を解消するため、共有者全員が納得できないケースもありますが、法的に強制力のある解決策となります。
そして、共有物分割請求訴訟を提起する際には、あらかじめ不動産に詳しい弁護士に相談をし、思わぬ判決が下されないためにもしっかりと準備をして臨むことが大切です。
共有物分割請求訴訟では、原則として、現物分割または賠償分割(全面的価額賠償)による分割が判決で言い渡されます。(民法258条2項を参照)ただし、現物分割や賠償分割ができない場合などには、換価分割をすることができます。
1.共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2.裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一.共有物の現物を分割する方法
二.共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3.前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4.裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
共有物分割請求を弁護士に依頼するメリット
共有物分割には法的な知識と調整が不可欠であり、弁護士のサポートが必要な場面が多くあります。
法的手続の適切な進行
弁護士は、不動産の共有者が増え続けている場合や、複雑な代償分割が必要な場合などでも、スムーズに解決を進めるための書類作成や調停・訴訟手続を代行します。
話合いでは解決できなかった共有状態を解消するために訴訟を提起した場合には、それぞれの言い分をただ言い合うのではなく、法律的な根拠に基づいて主張・立証する必要があります。
しかし、どのような証拠が重要な証拠なのかは、訴訟の経験がない人だと分からないということもあります。その点で弁護士は、ご依頼者の方に代わり、請求相手や裁判官に対して法的根拠に基づいた主張をし、より納得できる解決に近づけることができます。
感情的な対立の緩和
共有者間で争いになることは避けたいと考え、不満があっても共有状態のまま放置してしまう方もいらっしゃいます。
しかし、時間が経てば経つほど、共有状態は複雑になっていくこともあるため、話合いは困難を極め、以前からの不満等もあれば感情的な対立は避けることが難しい場合もあります。このような場合に、弁護士が代理人として相手方と交渉を進めることで、当事者同士の直接的な対立を避け、冷静な対応が可能になります。
公平な分割の実現
代償分割や換価分割の場合、不動産の適正な評価が重要です。不動産の評価額などで、共有者間で意見が違う場合、最終的な解決までには多くのやり取りを繰り返すことになり、時間的にも精神的にも負担がかかってしまいます。
弁護士に依頼することで、弁護士は適切な価格を査定し、共有者間で公平な分割を図るサポートを行います。結果としてご自身の負担を減らすことにもつながります。
弁護士に依頼することで生じるデメリット
弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用がかかるという点になります。弁護士に依頼すると、どの程度費用がかかるのかについては、初回のご相談時に弁護士にお尋ねください。
ご自身で共有物分割請求をしたものの、法律上正しい買い取り金額なのか分からず共有持分を買い取ってもらうと、解決した後も、心に引っかかり続けるかもしれません。 ぜひ、ご自身が納得できる解決方法を選択していただければと思いますので、ご不明点や不安に感じられている点は、遠慮なく弁護士に相談してください。
不動産の相続に関する相談は、弁護士法人シーライトへ
共同相続した不動産の共有状態を解消するには、現物分割、代償分割、換価分割の方法があり、調停や訴訟を利用した解決も可能です。しかし、これらの手続には法律の専門的な知識が求められます。
相続に詳しい弁護士の適切なアドバイスと手続のサポートにより、共有不動産の解消がスムーズかつ公平に行われ、将来のトラブルを回避することができます。不動産の相続でお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
 弁護士法人シーライト
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は500件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介