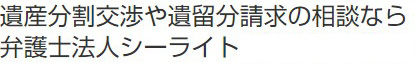特別受益の持戻しとは? ~特別受益と認められるものと認められないものについて~

兄弟姉妹の中で、生前に親から結婚式の費用として300万円を贈与された子どもと未婚であったためにそのような贈与を受けなかった子どもがいる場合、相続時その生前贈与を考慮せずに相続財産を均等に分けるとしたら、贈与を受けていない子どもは不公平感に感じかもしれません。このように不公平な状態となってしまうことを考慮して、民法では特別受益という制度を設けています。特別受益の持戻しを行うことで、相続人同士の不公平を無くすことができます。
今回は、特別受益の持戻しとは何なのか、特別受益と認められるものと認められないものについて解説します。
目次
特別受益とは?
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与を受けたり、遺言によって遺贈を受けたりして得た特別な利益のことを指します。そのため特別受益は、遺産の前渡し分と考えることができます。民法903条1項では、特別受益を以下のように規定しています。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
つまり、特別受益があった場合、相続開始時には、相続財産の額と特別受益の額を合算して各相続人の相続分を決め、遺産を公平に分けることになります。
特別受益の持戻しについて
特別受益の対象となった財産は、相続の際にその価額を相続財産へ加算したうえで遺産分割を行います。これを特別受益の持戻しといいます。簡単にいえば、特別受益分を相続財産の計算に入れることが持戻しです。また、特別受益の評価基準時は、民法には規定はありませんが、実務上では、相続開始時の評価額で判断しています。
物の価額は、変動していることがほとんどです。そのため、生前贈与を受けた時の価値ではなく、相続開始時の価値で特別受益の評価をします。
また、金銭で贈与を受けた場合にも、生前贈与と相続開始時にかなりの時間差があるような場合には、貨幣価値も当然変動していますので、消費者物価指数をもとに、贈与時点の金銭価格が相続開始時にいくらになっているのかを算定することになります。
たとえば、相続財産が5,000万円の場合で、子どもである長男と次男の2人が相続人だとします。
長男だけが1,000万円の生前贈与を受けました。この長男が受けた生前贈与を特別受益とみなし、特別受益の持戻しを行うと、みなし相続財産は5,000万円+1,000万円=6,000万円となります。
※遺産総額に特別受益分を合算したものをみなし相続財産といいます。
相続人が2人の子どもだけの場合は、法定相続分は1/2ずつとなります。長男は、生前贈与を受けているため、みなし相続財産に法定相続分である1/2を乗じたうえで特別受益額1,000万円を差し引きます。
6,000万円×1/2-1,000万円=2,000万円
一方次男は、特別受益を受けていないので、6,000万円×1/2=3,000万円が相続分となります。
もし、特別受益の持戻しをせず、法定相続分通りに相続するとなった場合には、相続財産5,000万円を1/2ずつ相続するので、長男も次男もそれぞれ2,500万円を相続することとなります。長男に関しては、被相続人の生前に1,000万円を受け取っているので、このように特別受益の持戻しをしなければ、次男の立場としては、不満を感じることもあると思います。
そのため特別受益の持戻しをすることで、相続人間の不公平を解消することができます。
特別受益者の範囲について
特別受益を受けた人を特別受益者と呼びます。特別受益者は、高額な生前贈与などを受けた全員が対象ではなく、被相続人との関係から一定範囲に限られます。主な特別受益者は、推定相続人や推定相続人になる予定の人、代襲相続人、相続人の配偶者や親族です。
推定相続人について
推定相続人とは、法定相続人となる予定の人のことです。推定相続人が特別受益を受けていた場合には、特別受益者となります。
推定相続人になる予定の人について
推定相続人になる予定の人とは、婚約者や養子になる予定の人です。通説では、推定相続人になる予定の人は、相続開始時に相続人であったならば、受益の時期にかかわらず、すべてが持戻しの対象になると解されております。
代襲相続人について
法定相続人となる被相続人の子どもが、相続開始前に死亡していた場合、その子どもに子(被相続人からみた孫にあたる人)がいれば、代襲相続人となります。代襲相続人は、亡くなった子ども(代襲相続人からみて親にあたる人)に代わって、相続権を引き継ぎます。
もし、代襲相続人になる可能性のある人が代襲原因(被代襲者の死亡・相続欠格・相続廃除)発生前に、被相続人から贈与を受けたという場合には、その時点では推定相続人でないため、原則として特別受益者にはなりません。ただし、実質的に被代襲者への遺産の前渡しと評価できる特段の事情がある場合は持戻しの対象となりえます。代襲原因発生後に関しては、代襲相続人は推定相続人となるため、代襲原因発生後の生前贈与に関しては、内容によって特別受益者になる可能性があります。
相続人の配偶者や親族について
特別受益の制度は、原則として、法定相続人や推定相続人に対しての制度であるため、相続人の配偶者や親族が特別受益者になることはありません。しかし、相続人の配偶者等へ名義上の贈与が行われ、その贈与によって配偶者ではなく、相続人が利益を得ていた場合には、その相続人への贈与とみなされ特別受益が考慮される可能性もあります。
特別受益と認められるものとは
特別受益の対象となるものは、民法では下記のようなものが対象となると明記されています。
全ての遺贈
婚姻費用の贈与
養子縁組のための贈与
生計の資本としての贈与
遺贈について
遺贈とは、遺言者が遺言によってその一方的意思により行う財産処分のことをいいます。遺贈は、贈与と似ていますが、贈与は、受け取る側(受贈者)の承諾が必要であるのに対し、遺贈は、遺言の一種であるため、受遺者の承諾は必要なく、遺言者の一方的な意思表示で行うことができます。そのため、遺言によって初めて受遺者となる人が、遺贈されることを知るという場合もあります。
また遺贈は、相続人でも相続人以外の人や法人などに対しても行うことができます。
婚姻費用や養子縁組のための費用の生前贈与
婚姻費用には、持参金、支度金、結納金や挙式費用など様々あります。少額であれば扶養義務の範囲内とみなされるので、特別受益にあたる可能性は低いと思われます。高額な支度金や持参金の場合には、特別受益と考えられます。結納金は、結婚相手への贈与となるため、一般には特別受益にあたらないと考えられています。挙式費用についても、相続人に対する遺産の前渡し分とは判断せず特別受益にはあたらないと考えられています。
また、普通養子縁組によって養子となった子どもに対して、実の親から高額な遺産の前渡しをされた場合には、養子は、実親の特別受益者となる可能性があります。
生計の資本としての贈与
不動産の購入資金を贈与、事業を始めるための開業資金の生前贈与等、ある程度まとまった金額の贈与である場合には、生計の資本として認められることが多いと思われます。生計の資本であるかどうかの判断は、贈与の金額や贈与の趣旨などから総合的に判断されます。
学費に関しては、特別高額な教育費や海外留学の費用を援助したという場合でなければ、被相続人の扶養義務の範囲内であり、特別受益にはあたらないと考えられます。そのため、学費については、被相続人の資力や他の相続人との比較等によって特別受益にあたるかを判断します。
その他の贈与についても特別受益の対象となるケースについて
上記のものだけではなく、その他の贈与についても特別受益の対象となるケースがあります。
金銭・有価証券・金銭債権の贈与
扶養の範囲内の資金援助であれば特別受益には該当しませんが、高額な金銭や有価証券、金銭債権などを贈与した場合には、特別受益になる可能性が高いです。
生前に借地権の設定、承継をした場合
被相続人の土地に相続人の建物があり、借地権が設定されている場合には、借地権相当額の贈与があったとみなされ、特別受益に該当する可能性があります。また、借地権名義を被相続人から相続人に書き換えた場合にも、借地権相当額の贈与とみなされます。
しかし、何が特別受益にあたるのかは、判断が難しい問題です。
行われた生前贈与が特別受益にあたるかどうかは、被相続人の収入、生活状況や教育水準などによって判断が分かれます。また、過去の事案や判例などに即した判断が必要となります。特別受益かどうかご自身での判断が難しい場合は、弁護士など法律の専門家にアドバイスを求めることも1つの方法になります。
生命保険金や死亡退職金は特別受益の対象になるのか?
相続人が受取人になっている生命保険は、受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象でもないため、原則として特別受益には該当しません。したがって、その生命保険金額を相続財産に持戻す必要はありません。しかし、相続財産が生命保険のみであったり、生命保険金額が、相続財産に対して大きな割合を占めていたりする場合には、相続財産に持戻すことがあります。生命保険金額を相続財産に持戻すことを認めた裁判例もあります。
遺族に支払われる死亡退職金は、賃金の後払いと遺族の生活保障という二つの性格があります。そのため、どちらの性格が重視されるものかによって特別受益の考え方も変わりますので、退職金規定等の確認が必要となります。もし、賃金の後払いという場合なら相続財産に持戻し、遺族の生活保障という場合なら相続財産にならないので持戻さないとなります。また、一部の相続人だけが多額の死亡退職金を受け取った場合も、特別受益とみなされる可能性があります。
特別受益の時効について
特別受益の持戻しをするうえで、特別受益に時効はあるのか気になった方もいるかもしれません。特別受益の持戻しに時効や期限はありません。
ただし、注意しなければならないのが、2023年4月1日施行の民法から、相続開始時点から10年が経過すると特別受益の主張ができなくなります。少しややこしいですが、20年、30年以上前やもっと古い特別受益であっても、持戻して計算することが可能です。持戻しできる特別受益の期限はないのですが、相続開始から10年経過後に行う遺産分割協議では特別受益を主張できません。
つまり、10年以上被相続人の遺産分割協議を進めないまま時が経ってしまうと、特別受益の主張ができなくなる可能性があります。
特別受益と認められる生前贈与は、必ず持戻しが必要なのか?
生前贈与が行われる前に他の相続人に理解を得る
もし特別受益があった場合には、必ず持戻しをする必要があるのか?という疑問を持たれる方もいるかもしれません。原則としては、特別受益がある場合、特別受益の持戻しを行って不公平を解消する必要があります。
民法第903条1項では、特別受益者の相続分に関して、特別受益が認められる場合には持ち戻しをして相続分を計算するように規定されています。
ただし、特別受益にあたる生前贈与に対して、他の相続人が誰も特別受益を主張しない場合には、持戻しをせずに遺産分割を進めることもできます。被相続人の子どもの1人に対してだけ生前贈与を行った場合でも、その生前贈与を行った理由を他の子どもに説明し、納得してもらえば、特に相続時に特別受益として持戻しをする必要はありません。
持戻し免除の意思表示があった場合
被相続人が遺言などで持戻しの免除の意思表示をした場合に、原則として贈与や遺贈を受けた相続人は、持戻す必要がありません。つまり、被相続人から遺言などで「〇〇に贈与した財産を相続財産に加算しないでほしい」という意思表示がされれば、特別受益があったとしても持戻しをせず、被相続人の意思に従うことになります。これを持戻し免除の意思表示といいます。
ただし、その生前贈与や遺贈によって、他の相続人の遺留分が侵害される場合には、遺留分を算定するにあたって、その特別受益にあたる生前贈与や遺贈を相続財産に持戻して算定する必要があります。遺留分は、遺言よりも優先される相続人の権利であるため、持戻しを免除された特別受益があったとしても、それにより他の相続人の遺留分が侵害される場合には、遺留分侵害額請求をされることがあります。
遺留分侵害額請求は、その侵害されている相続人からの請求があれば応じる必要がありますが、必ず請求がなされるものでありません。ちなみに、持戻し免除の意思表示の方法については、法律上定めはありません。免除の意思表示は、口頭でもよく、被相続人は免除の意思表示をした後でも自由に免除の意思表示を撤回することができます。
意思表示の方法に決まりはないとはいえ、特別受益の免除意思が口頭の場合、本当に被相続人の免除の意思表示が有ったのかどうなのかについて、相続開始時に争いが起きる可能性もあります。その意思が有ることを認めてもらうためには証拠が必要となるので、遺言に明示しておく方が、後々の争いを避けるためにも良いかと思います。遺言には、「遺言者〇〇〇〇は、○年○月○日、X氏に対し金1,000万円を贈与したが、民法903条1項に規定する相続財産の算定にあたっては、当該贈与額は、相続財産の価額に加えないものとする。」というように記載しておくと良いでしょう。
婚姻期間20年以上の配偶者に自宅を贈与した場合
2019年7月1日に施行された改正民法から適用になったもので、婚姻期間が20年以上の夫婦間で同居していた家や土地が遺贈または贈与された場合は、原則として持戻しの免除の意思表示があったものと推定することにしました。これは、第903条第4項の部分に規定されています。
4.婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
※ただし、確実に認められるというわけではありません。
2019年の民法改正前は、長年連れ添った配偶者が生前に自宅を譲り受けていた場合でも、それは特別受益として持戻す必要があり、遺産分割において、取得額が減額されることがありました。しかし今回の法改正により、夫婦間の自宅贈与であれば、特に書面に特別受益の持戻しの免除の意思表示を残す必要がなくなりました。
特別受益と遺留分の関係について
相続人が複数いる中で、一部の相続人に対して生前財産のほとんどを贈与している場合は、贈与を受けていない他の相続人の遺留分を侵害している可能性があります。特別受益によって相続人の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害請求をすることができます。ただし、遺留分の計算において、特別受益の対象となる贈与は、すべての贈与ではありません。
それは、相続開始前の1年前になされた贈与、相続人に対して10年前までになされた贈与、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与に限られます。遺留分侵害額請求の場合の贈与と遺産分割時における特別受益の扱いが異なるためこの点で注意が必要です。たとえば、相続分の計算について、持戻しできる特別受益に時効や期限はないため、20年前の特別受益も計算に入れることができます。しかし、遺留分計算に含めることができる特別受益は、相続開始前10年以内のものに限定されているため、20年前の特別受益は計算に入れることができません。このような違いがあります。
特別受益がある相続は弁護士にご相談ください
生前贈与がある場合には、特別受益に該当するかどうか、ご自身での判断が難しい場合もあります。遺産分割の際に、生前贈与などが特別受益にあたるかどうかで相続人同士でもめてしまいそうな場合(もしくは、もめている場合)には、相続に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士であれば、遺産の調査を行い、特別受益がないかどうかを調べ、ご依頼者様の代理人として遺産分割協議に参加し対応することができます。特別受益がある相続でお困りの場合は、弁護士法人シーライトにご相談ください。
 弁護士法人シーライト
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は500件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介