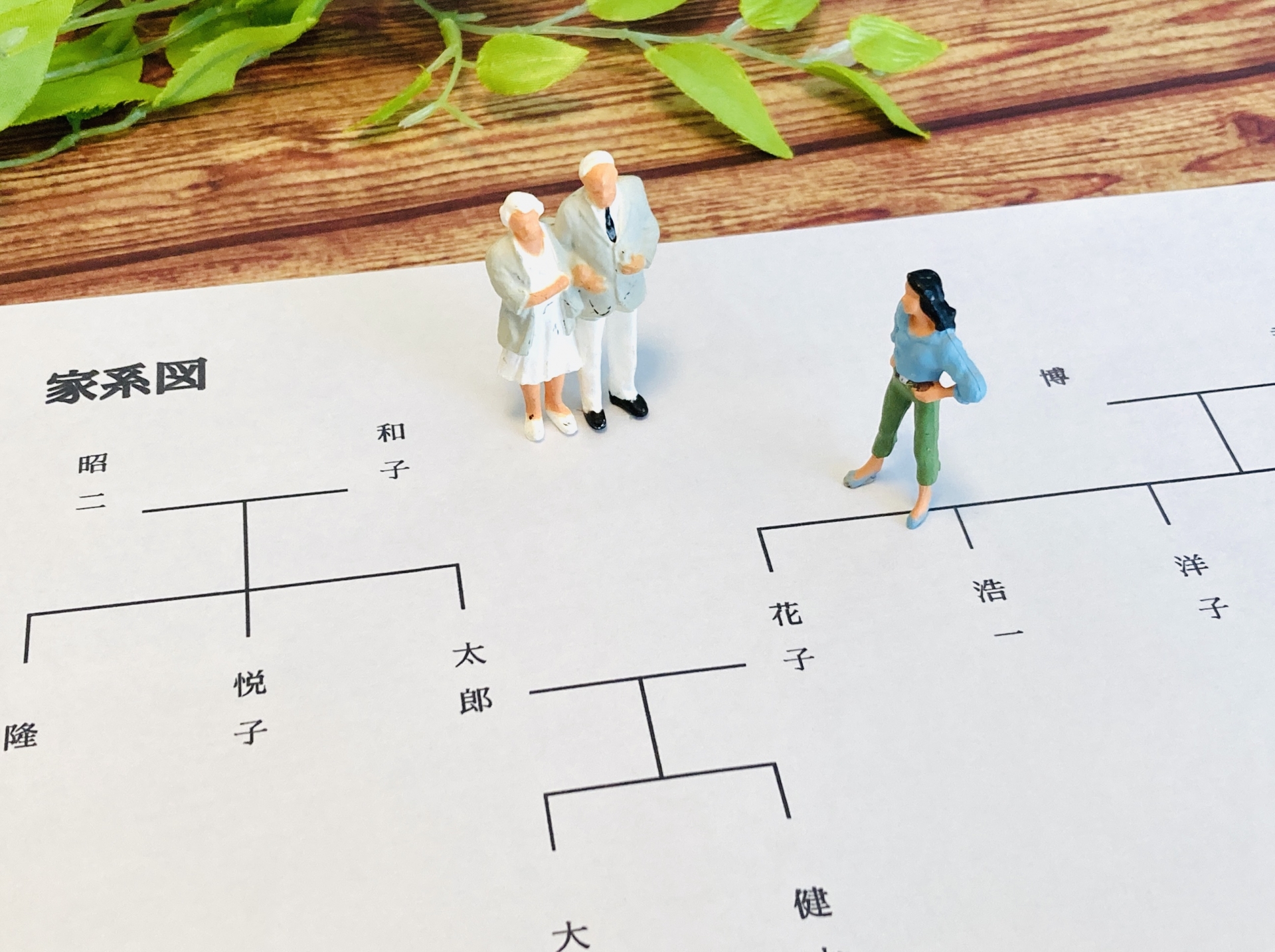遺留分は、配偶者、直系卑属(子どもまたは孫など)、直系尊属(親または祖父母など)の中で、相続人になっている人に認められる最低限の遺産の取り分のことです。
遺留分に関する記事は何度か紹介したことがありますが、今回は、子どもの遺留分について知っておきたい基礎知識をご紹介します。
子どもには遺留分が認められている
遺留分は、被相続人の子どもにも認められている権利です。そのため、遺言の内容が、遺産を子どもには渡さないような内容となっていたとしても、被相続人の子どもには遺留分相当額のお金を受け取る権利があります。遺留分の権利を有する子どもが複数いるにも関わらず、遺言書の内容が特定の人物にのみ遺産を相続させるような内容のため、他の相続人の遺留分が侵害され問題となっているケースが多々あります。そのような場合には、遺留分を侵害している相手に対して遺留分侵害額請求をすることで、遺留分を取り戻すことになります。
遺留分とは
民法で定められた特定の相続人に保障されている最低限の遺産の取り分です。遺留分は、配偶者・子ども・直系尊属の相続人に保障されています。子どもについては、被相続人の実子だけでなく、非嫡出子も含まれます。また、被相続人の子どもが被相続人よりも先に他界している場合で、被相続人の子どもに子どもがいた場合には代襲相続することができます。
遺留分の特徴
遺留分には以下のような特徴があります。
- 廃除された相続人には、遺留分は認められません。
- 相続欠格の該当者には、遺留分は認められません。
- 相続放棄をした場合には、遺留分は認められません。
- 被相続人であっても、相続人の遺留分の権利を奪うことはできません。
- 被相続人の兄弟姉妹、甥や姪に遺留分はありません。
子どもの遺留分に関して関係があるのは、上記の1~4の項目となります。
子どもが相続廃除、相続欠格、相続放棄した場合には遺留分の権利はなくなります。ただし、相続廃除と相続欠格の場合には、代襲相続が認められていますので、もし被相続人の子どもが相続廃除や相続欠格で遺留分を請求する権利がない場合でも、その人物に子どもがいれば(被相続人から見て孫にあたる人物)、代襲相続をして遺留分を請求することができます。
子どもの遺留分の計算方法
遺留分の計算式は、遺留分の基礎となる財産合計に個別の遺留分割合を乗じたものになります。子どもの遺留分を算出する場合には、個別の遺留分の割合の部分に子どもの遺留分割合を当てはめて計算します。

遺留分の計算の対象となる財産について
遺留分の対象となる財産は、被相続人が有していた財産だけではありません。被相続人の生前の贈与なども遺留分の対象となります。
遺留分算定の対象となる財産の合計は、被相続人が有したプラス相続財産に条件付きの権利や遺贈、死因贈与、生前贈与、不相当な対価をもってした有償行為、特別受益などを足した額から借金などの負債を差し引いたものとなります。
相続開始時に有していたプラスの財産とは
被相続人が相続開始時に有していたプラスの財産には、以下のようなものがあります。
- 不動産と不動産上の権利です。たとえば、宅地、農地、建物、店舗、居宅、借地権、借家権などが該当します。
- 動産もプラスの財産の対象となり、自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品などが該当します。
- 現金、有価証券、預貯金、貸付金、売掛金、小切手など
- その他に電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権などもプラスの財産の対象となります。
生前贈与について
全ての生前贈与が遺留分の侵害の対象となるわけではありません。下記のような生前贈与がある場合には、遺留分侵害額請求の対象になります。
- 相続開始前1年間の相続人以外への生前贈与
- 相続開始前10年以内の法定相続人への特別受益にあたる生前贈与
- 他の相続人の遺留分を侵害していると知って行われた生前贈与
① 相続開始前1年間に行われた相続人以外への生前贈与について
被相続人が亡くなる前の1年間に行われた相続人以外への生前贈与は、相続財産として判断されます。 相続人以外とは、相続人ではない親族や慈善団体などの組織や他人などになります。
② 相続開始前10年以内に行われた法定相続人への特別受益にあたる生前贈与について
特別受益にあたる生前贈与が法定相続人に対して行われた場合に、相続が開始される前の10年間については、遺留分の対象となります。特別受益にあたる生前贈与とは「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」や「生計の資本としての贈与」に限ります。
婚姻、養子縁組のための贈与について
持参金、支度金や嫁入り道具などです。ちなみに、挙式費用は通常、特別受益には含まれません。
生計の資本としての贈与について
扶養義務履行の範囲を超えた生活費、不動産・車などの購入資金、独立開業に際しての運転資金、住宅購入資金、大学の学費(※)が該当します。
※ただし、医学部など高額な場合でないと特別受益とはされないことが多いです。
生前贈与が、特別受益に該当するかどうかは、贈与額、贈与の動機、時期等のさまざまな事情から判断されることになります。そのため、何が特別受益にあたり、何が特別受益でないのかは、相続の事案ごとに判断する必要が出てきます。ご自身での判断が難しい場合は、相続に詳しい弁護士にご相談ください。
③ 他の相続人の遺留分を侵害していると知って行われた生前贈与について
遺留分権利者の遺留分を侵害することを知って行われた生前贈与については、特に期間は設けられておらず、無期限となっています。つまり、③の生前贈与に関しては、すべてが遺留分の計算の対象となります。また「他の相続人の遺留分を侵害していると知っていた」とは、その事実関係を知っていればよいとされています。
被相続人のマイナスの財産(負債)とは
被相続人に負債がある場合は、その全額を差し引きます。 負債には以下のようなものがあります。被相続人が負っていた債務のみが対象となります。
- 負債には、借金、買掛金、住宅ローン、小切手などがあります。
- 税金関係には、未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金などがあります。
- その他、未払い分の家賃・地代、未払い分の医療費などがあります。
子どもの遺留分割合について
各相続人の遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。子どもがいる場合の遺留分の割合については下記のようになります。
| 相続人の構成 | 各相続人の遺留分割合 | |
|---|---|---|
| 配偶者 | 子ども | |
| 配偶者と子供 | 1/4 | 1/4の人数割 |
| 子供のみ | 1/2の人数割 | |

配偶者と子どもが相続人の場合
相続人が配偶者と子どもの場合には、原則として遺産の全部を配偶者と子どもが相続します。法定相続人第2順位の父母と法定相続人第3順位の兄弟姉妹は、相続人にはなれません。そのため、父母と兄弟姉妹には、遺留分を請求する権利もありません。 総体的遺留分は、相続財産の2分の1となります。
子どものみが相続人の場合
相続人が子どものみの場合は、原則として遺産のすべてを子どもが相続することになります。 法定相続人第1順位の子どもがいるため、父母や兄弟姉妹は、遺産を相続することができません。遺留分を請求する権利もありません。 総体的遺留分は、相続財産の2分の1となります。
子どもがいる場合の遺留分の計算例
1. 相続人が配偶者と子ども1人の場合
子どもの遺留分は、4分の1になります。遺留分算定基礎財産が6000万円の場合、子どもの遺留分は、1500万円です。
1-1. 配偶者に高額な相続がある場合
もし、配偶者に対して6000万円の4分の3にあたる4500万円より多い額の財産が遺言で相続された場合、子どもに相続される額は、1500万円を下回ります。そうなると子どもの遺留分は侵害されている状態となるため、侵害されている分の額を請求することができます。
たとえば、配偶者に遺言で5000万円が相続された場合、子どもには、1000万円しか相続されません。その場合、子どもの遺留分が500万円分侵害されている状態になります。そのため、子どもは、500万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
1-2. 相続人以外に高額な遺贈や生前贈与があった場合
相続人は、配偶者と子ども1人の時、相続人以外に多額の遺贈・生前贈与があった場合には、残りの財産を分けることになります。たとえば、遺留分算定基礎財産が6000万円で、相続人以外の人に3500万円分の財産が遺贈されたとします。そうなると、残りの財産は、3000万円を下回ることになります。この場合、2500万円の財産を配偶者と子どもで分けることになりますが、2500万円の2分の1を取得したとしても、遺留分にあたる1500万円を下回る額となり、子どもは、足りない分の遺留分を請求することができます。
2. 相続人が子ども1人の場合
相続人が子ども1人の場合には、遺留分の割合は、2分の1となります。遺留分算定基礎財産が6000万円の場合には、子どもの遺留分は、3000万円となります。例えば、被相続人が子ども以外の人に3500万円を生前贈与していた場合、子どもには2500万円が相続されます。その場合、子どもの遺留分が500万円分侵害されることになります。そのため、子どもは500万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
3. 相続人が配偶者と子ども2人の場合
子どもの遺留分は、全体で4分の1なので、子ども1人あたりの遺留分は、1/4÷子ども2 人で1/8となります。遺留分算定基礎財産が6000万円の場合、子ども全体の遺留分は、1500万円となり、子ども1人あたりの遺留分は750万円になります。
3-1. 配偶者に対して高額な相続があった場合
もし、遺留分算定基礎財産が6000万円で、被相続人の配偶者に対して4500万円を超える財産が相続された場合、残りの財産は1500万円を下回り、子どもの遺留分が侵害されることになります。例えば、配偶者に遺言で5000万円が相続された場合、子ども2人には、あわせて1000万円が相続されます。子ども1人あたりでは、500万円が相続されることとなり、その場合、子ども1人の遺留分は、250万円分侵害されることになります。
3-2. 1人の子どもに多額の相続や生前贈与があった場合
被相続人の財産の合計が6000万円の場合、子ども2人のうち1人の子どもに対して3750万円を超える財産を相続、生前贈与等していた場合、もう1人の子どもは、遺留分を下回る額しか取得できないため、遺留分侵害額請求することができます。なぜなら、もう1人の子どもは、2250万円未満の残りの財産を配偶者と分けることになります。法定相続の割合で分けた場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分は、4分の1となります。そのため、もう1人の子どもの取得財産は、750万円を下回る額となります。
3-3. 相続人以外に多額の遺贈や生前贈与があった場合
相続人以外の人物に対して遺贈や生前贈与があった場合には、残りの財産を配偶者と子ども2人とで分けることになります。たとえば、遺留分算定基礎財産が6000万円の時、相続人以外の人に対して、3000万円を超える財産を遺贈・生前贈与した場合、残りの財産を配偶者と子ども2人で分けることになります。子どもの法定相続分である4分の1を取得したとしても、750万円を下回る額となり、子どもの遺留分に達しません。
4. 相続人が子ども2人の場合
子どもの遺留分は、全体で2分の1なので、子ども1人の遺留分は4分の1となります。遺留分算定基礎財産が6000万円の場合、子どもの遺留分は全体で3000万円となり、子ども1人あたり1500万円になります。
4-1.1人の子どもに多額の相続や生前贈与があった場合
被相続人が1人の子どもに遺留分算定基礎財産である6000万円の4分の3にあたる4500万円を超える財産を相続や生前贈与した場合、もう1人の子どもの遺留分が侵害されることになります。なぜなら、たとえば1人の子どもに5000万円を相続生した場合、もう1人の子どもは1000万円しか相続することができません。そうなると遺留分が500万円分侵害されることになります。
4-2.相続人以外に多額の遺贈や生前贈与があった場合
例えば、遺留分算定基礎財産が6000万円のとき、相続人以外に3000万円を超える財産を生前贈与していた場合、子どもの遺留分は侵害されることになります。子どもは、3000万円を下回る残りの財産を2人で分けることになりますが、法定相続分である2分の1を取得しても、1500万円に届かない額となります。そのため、遺留分を侵害された分を、遺留分を侵害している相手方に請求することができます。
5.相続人が子ども3人の場合
配偶者が存命の時の、子どもの遺留分は全体で4分の1なので、子ども1人あたりの遺留分は、12分の1になります。もし、配偶者が他界している場合は、子どもの1人あたりの遺留分の割合は、6分の1になります。子どもの3人の場合の遺留分についての計算方法は、上記で述べた子ども2人の場合と同様の計算になります。
遺留分が侵害されていた場合の対処法について
子どもの遺留分が侵害されていた場合には、遺留分侵害額請求を行い、遺留分を取り戻します。子どもは、遺留分を請求する権利を有しているだけですので、請求をしなければ遺留分は取り戻せません。遺留分侵害額請求の意思表示方法について、特に決まりはありませんが、確実に意思表示をしたと証明できる「配達証明付内容証明郵便」で行うのが一般的です。また、遺留分侵害額請求を行うのには、期限があります。その期限が過ぎないように早めに手続きをすることをおすすめします。
遺留分侵害額請求を侵害している相手に行う流れについて
遺留分を請求する権利を持っているのは、配偶者、子ども、両親になります。兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害している人に対して、通知をすることです。遺留分侵害額請求の意思表示方法については、特に形式がありません。そのため、口頭、手紙、メールなどで伝えることもできます。しかし、のちのち裁判に発展した場合に、遺留分侵害額請求をしたことを証明できるために「配達証明付内容証明郵便」で行うのが一般的です。
遺留分侵害額請求をしたものの、遺留分を侵害している相手が、すぐに遺留分の請求に対して対応してくるというわけではありません。そのため、遺留分侵害額請求をした後は、交渉、遺留分侵害額請求調停、遺留分侵害額請求訴訟といった方法で相手に遺留分の請求を行います。遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害している人が複数人いる場合には、それぞれに請求しなければならない点で注意が必要です。例えば、相続人のうち遺留分を侵害している人が2人いる場合には、どちらか一方に請求すればよいのではなく、それぞれに、遺留分侵害額請求をしなければならないため、それぞれに請求するための遺留分侵害額を計算する必要があります。
遺留分侵害額請求の期限について
注意しなければならないのが、遺留分侵害額請求ができる期間には限りがあります。遺留分を請求するできる期間は、①相続の開始と、②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年以内となっています。それ以後の遺留分侵害額請求はできません。ただし、遺留分権利者が相続開始を知ってから1年間にあてはまるとしても、相続開始の時から10年が経っている場合には、時効によって消滅します。また、遺留分侵害額請求を行った後にも、時効があるため、注意が必要です。遺留分侵害額請求を行使してから5年間経つと、金銭支払請求の権利が消滅します。
時効:相続開始と遺留分侵害を知ってから1年
遺留分侵害額請求の時効は、①相続が開始したこと、②遺留分が侵害されていること(侵害されていたこと)を知ったときから1年です。消滅する時効は、①と②の両方を知ってから1年となります。しかし、裁判になった場合にはいつ遺言の存在を知ったかを証明することが難しくなるため、できるだけ、被相続人の亡くなった日から1年以内に権利行使をするのがおすすめです。ちなみに、1年の消滅時効については、遺留分侵害を請求される人が消滅時効を主張しなければ、時効を迎えた後も請求は可能となります。遺留分侵害額請求の時効は、相手方に遺留分侵害額請求をした時点で止まります。
消滅:相続開始から10年
遺留分侵害額請求権は、①相続が開始したこと、②遺留分を侵害するような遺贈や贈与などがあったことを遺留分権利者が知らなくても、相続が開始してから10年が経過すると消滅してしまいます。この期限を除斥期間と呼びます。
金銭支払請求権5年の時効
遺留分侵害額請求を行うと、遺留分侵害額を金銭で支払うように請求する「金銭支払請求権」が発生します。この金銭支払請求権は、遺留分侵害額請求権とは別の権利として、原則5年で時効となります。つまり、遺留分侵害額請求を期限内に行っていても、その後には別の時効が存在するので注意が必要です。遺留分侵害額請求権を行使した後に5年間何もしなければ、金銭請求はできなくなります。ただし、厳密にいうと、遺留分侵害額請求権を行使した時期によって時効期間が変わります。2020年4月1日施行の改正法で消滅時効のルールが変わりました。そのため、2020年3月31日以前に行使していれば10年、同年4月1日以降に行使していれば5年が時効となります。

遺留分の権利を失わせる方法について
最後に遺留分を減額したり、遺留分の権利を失わせたりする方法についてご説明します。例えば、「子どものうちの1人に全財産を譲りたい」「子どもとは縁を切っているから遺産を相続させたくない」など、相続人となる人の遺留分が侵害されるような内容の遺言書となりそうな場合には、遺留分について後々トラブルに発展しないようにするために、あらかじめ該当する遺留分権利者の遺留分の権利を失わせておくのが大切です。
1.遺留分の放棄について
遺留分の放棄は、相続放棄と違い、相続開始前の放棄が認められています。ただし、遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所での許可がないとできません。なぜなら、相続人本人の意思によって遺留分を放棄するのではなく、被相続人や他の相続人による強要などによって遺留分の放棄させられる可能性もあるため、相続開始前の遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可が必要となっています。ちなみに、相続開始後に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所の許可は必要ではなく自由にすることができます。また、遺留分を放棄したとしても、相続人の権利まで失うわけではありません。
2.相続廃除の制度
相続人廃除とは、推定相続人から相続権を剥奪する制度になります。相続人廃除のためには、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときに、被相続人が推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することが必要です。被相続人が家庭裁判所に推定相続人の相続人廃除の申立てをします。推定相続人とは、配偶者、子ども、直系尊属となります。ただし、相続廃除された人が被相続人の子どもの場合には、その子どもに子どもがいれば代襲相続をすることはできます。被相続人からみて孫にあたる人が、被相続人の子どもに代わって、遺留分権利者として被相続人の子どもが有していた遺留分の権利も引き継ぐことになります。
3.相続欠格の制度
相続人廃除と同じように、推定相続人から相続権を奪う制度には、相続欠格というものがあります。民法では、相続欠格について下記のように定めています。
民法891条 相続人の欠格事由
1 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格事由に該当した相続人は、裁判の手続などは必要なく、相続権を失います。また、相続欠格になった人は、遺贈を受けることもできなくなります。ただし、相続欠格の場合でも、相続欠格となった人に子どもがいれば、代襲相続することができます。
遺留分について不明なことがあれば弁護士にご相談ください
今回は、子どもの遺留分に焦点をあててご紹介しました。子供の遺留分は、原則保障されている権利となります。相続の際には、子どもの遺留分を侵害していないか、相続人が複数いる場合には、遺留分の割合に注意しましょう。遺留分が侵害されているかどうかを調べる際には、相続財産の合計を算出しなければなりません。もし財産の中に不動産や遺贈、生前贈与などが含まれている場合には、計算が複雑になります。遺留分について分からないことがあれば、相続に詳しい弁護士にアドバイスをもらうのも1つの方法です。遺留分を請求するのにも期限があり、いつまでも請求できる権利ではありません。確実に遺留分を受け取るためにも、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人シーライトでは、遺留分に関するご相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
相続の話し合いは、ほんの些細なきっかけから揉めてしまうことが意外と多いです。そのような場面で少しでもお力になるべく、初回相談は無料とさせていただいております。
参考動画
お気軽にご相談ください。
\初回50分間のご相談が無料/

弁護士法人シーライト
受付時間:平日9時~18時 | 相談時間:平日9時~21時
※まだお問い合わせしない場合 LINE友だち 追加がおすすめ!