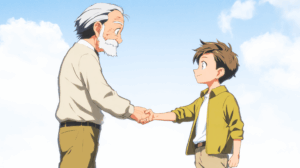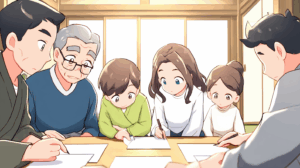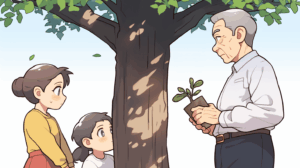相続財産の内容を把握するためには、相続財産の調査が必要です。
相続財産の調査について、積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)に分けて説明します。
積極財産の調査
積極財産の代表例は、預貯金、有価証券(証券会社で売買できる株や債券、投資信託など)、不動産、動産などです。
預貯金、有価証券
預貯金に関しては、金融機関ごとに調べる必要があります。預貯金通帳やキャッシュカードから金融機関を調査し、それぞれの機関で残高証明書と取引明細書を請求します。
また、近年ではネット上の銀行に口座等を保有している場合もあり、通帳やキャッシュカードが発行されていないこともあるので、被相続人のメールなどを確認することも大切です。
銀行や証券会社で金融商品を保有している場合は、銀行や証券会社からの郵便物から、該当する金融商品取引業者を調査し、取引残高報告書を発行してもらいます。
発行の際には、被相続人の戸籍・相続人の戸籍・相続人の印鑑登録証明書といった証明書類を求められることもあります。
不動産
不動産に関しては、登記済権利証、登記識別情報、固定資産税納税通知書(課税明細書)を確認し、必要に応じて、市町村役場で発行してもらう名寄帳、固定資産評価証明書、法務局で発行してもらう登記事項証明書(登記簿謄本)などから、被相続人がどこにどのような不動産を所有しているか調査します。
動産、その他
動産は、車や宝石、貴金属、美術品等、ヨット、クルーザーなど一定の価値を有するものです。 その他、ゴルフ会員権、知的財産権なども相続財産ですのできちんと調査する必要があります。
消極財産の調査
銀行からの借入(住宅ローンなどや消費者金融会社からの借金)がある場合には、借入先の金融機関などが加盟する信用情報機関の信用情報に登録されます。信用情報の照会によって、金融機関などからの借入額を調べることができます。
信用情報機関は、3つあります。
開示請求の際には、ご参考にしてください。
CIC(指定信用情報機関)
クレジットカードの利用履歴や信販会社との取引履歴を開示したい方はこちら
JICC(日本信用情報機構)
消費者金融会社との取引履歴を開示したい方はこちら
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
銀行や信用金庫との取引履歴を開示したい方はこちら
財産の記録をエンディングノートに
せっかく蓄えた財産がご家族などの相続人の方に知られずにそのままになってしまうのを防止する方法として、エンディングノートに記録をしておくことをおすすめいたします。
エンディングノートに記録しておくことで、相続財産調査の負担が軽減されます。
エンディングノートとは
エンディングノートとは、もしもの時に備え、自分の死後・終末期の取り扱いに関する希望や、財産に関すること(どこの銀行に口座を開設しているのか、通帳の保存場所はどこなのかなど)、家族や周囲の人に伝えたいことを書き残すノートのことです。
相続人・相続財産調査のご紹介
相続財産には様々なものが含まれるうえ、相続人があらかじめ把握していないケースも多いです。
また「遺産分割協議書」や「財産目録」をつくるにあたり、銀行の残高確認や不動産の価格調査をする必要があり、何かと煩雑です。
弁護士がお客様に代わって、相続財産を調査することで、お客様は煩わしさから解放されます。
相続財産調査でお困りの方は、弁護士法人シーライトにご相談ください。