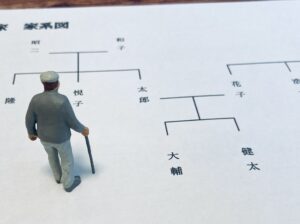はじめに
被相続人が亡くなり、遺産を相続する際、一定の場合には相続税という税金を支払う必要があります。
相続税という言葉に不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。被相続人が亡くなった後、降りかかる相続手続のなかでも、遺産が大きくなるケースでは、「相続税の申告をしなければならないのかどうか?」ということも考えなければいけません。
しかし、相続税は、すべての相続において課税されるわけではありません。相続税が課されるか否かを知る上で理解しておきたいのが、相続税の基礎控除額になります。これは、ある一定額までの財産には相続税をかけないという制度であり、制度の本質は「ご遺族の生活の安定」と「過度な税負担の回避」にあります。
本記事では、相続税の基礎控除とは何か、その計算方法や適用範囲、法定相続人の考え方などについて解説します。税理士や弁護士に相談する必要があるかどうか判断するための参考にもなる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
相続税の基礎控除額の概要
相続税の基礎控除額とは、相続税の課税対象となる財産総額から差し引くことができる非課税枠です。この基礎控除額を超えた部分の財産額に対して相続税が課税されることになります。
具体的には以下の式で算出されます。
この計算式により、法定相続人が増えると1人につき基礎控除額も600万円ずつ増えることになります。
つまり、法定相続人が1人であれば3,600万円、2人であれば4,200万円、3人であれば4,800万円となり、この金額までは相続税がかかりません。
基礎控除額の早見表は、下記の通りです。
| 法定相続人の人数 | 相続税の基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円 |
| 5人 | 3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円 |
相続税は現金で一括納付が原則
相続税の申告と納税の期限は10か⽉以内になります。この期間に申告書の作成とともに、納税資金の準備をしなくてはいけません。そして、納税は原則現金で一括支払いとなります。
しかし、相続税にはすべての遺産に課税することはせず、一定の額まで課税対象から外す制度(基礎控除)が設けられています。そうすることで、相続人の税負担を軽くしています。
平成27年改正で基礎控除額が縮⼩
相続税の基礎控除は、平成27年(2015年)1⽉に改正され、控除額が引き下げられています。
かつての基礎控除額は「5,000万円 +(1,000万円 × 法定相続人の数)」という計算式でした。しかし、平成27年1⽉の税制改正により、現在の「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」へ大幅に引き下げられました。
この改正により、相続税の課税対象者が一気に増え、「富裕層だけの税金」といわれていた相続税が、より多くのご家庭にも関係するものとなりました。
法定相続人の数が少ないご家庭では、基礎控除額が相対的に⼩さくなるため、遺産の総額がそれほど大きくなくても相続税の課税ラインを超えることがあります。例えば、相続人が⼦ども1名のみというケースでは、基礎控除額は、3,600万円にとどまるため、預貯金・不動産・株式等の合計額がこれを上回れば、相続税の申告手続が必要となります。
法定相続人の定義と数え方の詳細
相続税の基礎控除額を計算するうえで、法定相続人の数は重要です。しかし、相続人の範囲や扱いについては誤解されやすい点も多いため、詳しく解説します。
⺠法上の法定相続人の範囲
法定相続人とは、⺠法によって定められている、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人のことです。
この法定相続人の数によって相続税の基礎控除額が変わります。被相続人に配偶者がいる場合には、その配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人については、相続順位が定められています。
相続順位とは、第1順位から第3順位まであり、被相続人との関係性によって相続できる人とその順位が法律で決められています。順位の高い人が法定相続人となり、順位の低い人は法定相続人にはなりません。そのため、第1順位の⼦がいる場合、第2・3順位の者は相続人になりません。
具体的には、下記のような順位となっています。
| 相続順位 | 相続人 | 相続人が亡くなっている場合 |
|---|---|---|
| 必ず相続人になる | 配偶者 | なし |
| 第1順位 | 子ども(直系卑属) | 孫(代襲相続) |
| 第2順位 | 両親(直系卑属) | 祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(傍系卑属) | 甥姪(代襲相続) |
第1順位は、⼦どもになります。この⼦どもには、実⼦以外に養⼦・認知された⼦どもも含まれます。もし、⼦どもが被相続人の他界以前に亡くなっている場合には、孫(被相続人からみて)が法定相続人となります。これを代襲相続といいます。
第2順位は、両親である⽗⺟になります。もし、両親がすでに亡くなっている場合には、祖⽗⺟が法定相続人となります。この場合は、代襲相続ではありません。
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹になります。⼦どもの場合と同様に、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その⼦どもである甥・姪(被相続人からみて)が法定相続人となります。
計算方法の具体例
ここで具体的な例を使って、計算をしてみます。
ケース1:法定相続人が配偶者と⼦1人の場合
| 法定相続人の数 | 2人 |
|---|---|
| 基礎控除額 | 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円 |
| 相続財産総額 | 5,000万円 |
この場合、課税遺産総額は5,000万円−4,200万円=800万円となり、この金額に対して相続税が課されます。
ケース2:⼦が3人で配偶者がいない場合
| 法定相続人の数 | 3人 |
|---|---|
| 基礎控除額 | 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 |
| 相続財産 | 4,500万円 |
この場合は、相続財産が基礎控除額の範囲内であるため、相続税はかかりません。
法定相続人の人数に関する注意点
法定相続人が、上記で説明した場合のケースだけではなく、家族の中に養⼦がいる場合、相続を放棄した人がいる場合や代襲相続が発生した場合などのケースでは、法定相続人の人数を数える際に注意が必要となります。
それぞれのケースにおいて、法定相続人の数え方に関する注意点を紹介します。
養⼦縁組と基礎控除
養⼦は、実⼦と同じ第1順位の法定相続人になります。しかし、基礎控除の対象人数として養⼦を含める場合には、人数が以下のように制限されています。
- 被相続人に実⼦がいる場合:法定相続人に含められる養⼦の人数は1人まで
- 被相続人に実⼦がいない場合:法定相続人に含められる養⼦の人数は2人まで
また、たとえ上記の2つの制限内であっても、養⼦縁組の実態を伴わない税金対策のためだけの養⼦縁組は、税務署から否認され、法定相続人として認められない可能性もあります。
この養⼦の人数制限は、相続税の計算上にとどまり、⺠法上は養⼦の数に制限はありません。ちなみに特別養⼦縁組及び連れ⼦との養⼦縁組は、実⼦として認められるため、人数制限の対象外となります。
養⼦縁組であっても制限の対象外となる人
- 被相続人との特別養⼦縁組によって被相続人の養⼦になっている人
- 被相続人の配偶者の実の⼦どもであり、被相続人の養⼦になっている人
- 結婚前に特別養⼦縁組によって配偶者の養⼦になっており、結婚後に被相続人の養⼦になっている人
相続放棄した人がいる場合の基礎控除の取扱い
法定相続人が相続放棄すると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切を引き継がず、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。しかし、相続税の計算上では、相続放棄をした人も相続人として基礎控除額を計算します。そのため、相続放棄した人がいても、相続税の総額が増えることはありません。
例えば、法定相続人が4人いる場合、そのうち1人が相続放棄をしており、相続をしたのが3人であっても、基礎控除額の計算は、相続人4人として計算します。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円のままとなります。
なお、法定相続人が相続放棄した場合には、相続放棄した人の⼦どもは代襲相続することはできません。
相続放棄による相続順位変動時の注意点
前述したとおり、相続放棄をした人も法定相続人として相続税の計算をしますが、相続放棄によって相続順位が変わった場合には、気をつける点があります。
相続放棄によって法定相続人となる人が、次の相続順位の相続人に変わった場合でも、相続税の基礎控除額の計算上では、相続順位が変動する前の人数を法定相続人として数えます。
つまり、法定相続人が配偶者と被相続人の⺟親の2人のケースで、⺟親が相続放棄をした場合、第3順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。
被相続人には、弟が2人いたとします。その場合、相続税の基礎控除額を計算するうえでの法定相続人は、相続権が移る前の配偶者と⺟2人となり、配偶者と弟2人の3人ではありません。
相続欠格や相続廃除となった相続人がいる場合の基礎控除の取扱い
相続欠格や相続廃除となった相続人は、法定相続人に含まれません。そして、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の人数として数えることができません。これが、相続放棄した人のケースと違う点となります。
そのため、相続欠格や相続廃除により、相続税の基礎控除額が下がり、相続税の金額が上がることになります。しかし、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った相続人に⼦どもがいる場合には、代襲相続が可能です(再代襲は直系卑属に限ります)。
代襲相続人は、相続税の基礎控除額の法定相続人の数に含めることになります。
代襲相続が発生した場合の基礎控除の取扱い
代襲相続が発生した場合には、相続人の人数が変わる可能性がある点に注意が必要です。
代襲相続は、生きていれば相続人となった人がすでに他界していた場合に、その⼦どもが代わって相続人になることです。
例えば、被相続人には、配偶者と⼦どもが1人いたとします。しかし、被相続人の⼦どもは、被相続人よりも以前に亡くなっており、その⼦どもの⼦ども、つまり被相続人からみて孫にあたる人が遺産を相続します。
その孫が2人以上いる場合には、基礎控除額も増えます。仮に、孫が2人いた場合には、配偶者と孫2人で、法定相続人は3人となり、配偶者と被相続人の⼦どもが相続した場合と比べて、600万円分の控除額が増えることになります。代襲相続が起きても、1人あたり600万円の控除額が増えることに変わりはありません。
このように被相続人よりも先に法定相続人が亡くなっている場合は、代襲相続によって基礎控除額も変わるため、法定相続人を確定させることが必要です。
遺言書がある場合の基礎控除の取扱い
有効な遺言が存在しており、特定の法定相続人にだけ相続させるという旨の記載があった場合でも、相続税の基礎控除は法定相続人の数によって計算することになります。その税金を納める義務を負うのは、財産を相続した人になります。
また、遺言では、第三者に対しても財産を受け継がせる指定をすることができます。これを遺贈といいます。
このように被相続人の配偶者または一親等の血族(⽗⺟、⼦ども)でない人への遺贈は、相続税額にその20%相当額が加算されます。
例えば、相続権のない被相続人の孫が、遺贈によって財産を受け継ぎ、相続税額が500万円だったとします。このとき2割加算の原則により加算される金額は、500万円×20%=100万円となります。
最終的に、孫が納めなければならない相続税額は、500万円+100万円=600万円となります。
相続財産に含まれるもの
相続税の課税対象となる財産は、非常に多岐にわたります。相続税の対象となる財産の価額は、相続財産のうち、プラスの財産の価額からマイナスの財産の価額を差し引いたものになります。
プラスの財産には以下のようなものがあります。
- 預貯金・現金
- 不動産(自宅・賃貸物件・農地)
- 株式・投資信託などの有価証券
- 債権
- 自動車や貴金属・美術品などの動産
- 暗号資産
- 特許権や著作権などの知的財産権
一方で、マイナスの財産の代表例として、以下のようなものが挙げられます。
- 債務
- 未払いの住⺠税・所得税・公共料金など
このように、相続財産の全体像を把握したうえで、課税財産がどの程度あるのかをしっかり調査する必要があります。
相続財産の調査についての記事はこちらで詳しく紹介しています。


みなし相続財産の基礎控除における取扱い
相続財産ではない「みなし相続財産」も、相続税の課税対象になります。
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことを理由として受け取ることができる金銭等のことです。みなし相続財産とされるものには、死亡退職金や生命保険契約による死亡保険金などがあります。これらのみなし相続財産は、遺産総額の計算に含める必要があります。
ただし、死亡退職金や死亡保険金は、残された家族の生活保障という側面を持っているため、相続人が受取人である場合には、一定の額までは非課税となる枠が設けられています。
以下の計算式によって非課税となる限度額が定められています。
各非課税限度額
| 生命保険金 | 500万円 × 法定相続人の数 |
|---|---|
| 死亡退職金 | 500万円 × 法定相続人の数 |
相続税の計算の際には、遺産額に含める金額は保険金から非課税限度額を控除したあとの金額になります。
しかし、法定相続人でない人が死亡保険金を受け取った場合には、相続人ではないため、この非課税枠を利用することができません。
生前贈与の基礎控除における取扱い
一定の条件にあてはまる生前贈与は、相続税の課税対象となります。生前贈与とは、被相続人が生前に財産を贈ることです。相続税の課税対象になるのは、次のような対象への生前贈与です。
- 相続人
- 受遺者(被相続人から遺贈を受けた人)
- 死亡退職金や死亡保険金等を受け取った人
生前贈与の相続税の課税対象となる期間は以下のように定められています。
| 相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~2026年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡日までの期間 |
| 2031年1月1日~ | 相続開始前7年以内 |
例えば、2025年の〇⽉〇⽇の相続開始の時点で6,000万円の遺産があり、相続開始の2年前に被相続人から1,000万円を受け取っていた場合、課税対象となる遺産総額は7,000万円となります。
なお、上記の期間にあてはまる贈与だった場合でも、例外として特定贈与財産は相続税の対象になりません。
特定贈与財産とは、夫婦間において贈与された財産に対して、配偶者控除を適用し、相続税の課税対象から除外する財産のことです。この特定贈与財産とするためには、一定の要件を満たす必要があります。
- 婚姻期間が20年以上あること
- 居住用不動産またはその取得資金の贈与であること
- 贈与された翌年3⽉15⽇までに入居してそれ以降も引き続き居住すること
※贈与税はかかりませんが、贈与税の申告は必要です。上記の条件を満たすことで、相続税や贈与税が課税されることなく、居住用不動産やその取得資金を配偶者に贈与することができます。
相続時精算課税制度を利用した贈与の相続時の取扱い
贈与税の制度の1つである相続時精算課税制度を利用した贈与の場合、相続時にはどうなるのでしょうか。
相続時精算課税制度が改正され、改正法が2024年1⽉1⽇から施行されています。
相続時精算課税制度とは、基礎控除額110万円を超えた贈与に関して、累計2,500万円まで贈与税は課税されず、基礎控除額を控除した残額は、相続時に相続財産に加算され、相続税が課税されるという制度になります。
相続時精算課税制度の利用にも要件があり、下記のような要件となっています。
- 財産を贈与する人は、60歳以上の⽗⺟⼜は祖⽗⺟であること
- 財産を受け取る人は、18歳以上の贈与者の直系卑属である推定相続人または孫(養⼦を含む)であること
この制度を利用した場合には、被相続人の死亡時に、相続財産に加算して、相続税を計算しなければいけません。ただし、基礎控除額110万円以下であれば、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に贈与された財産であっても、相続財産に加算する必要はありません。
相続税の計算方法
相続税の基礎控除について説明をしてきましたが、ここから相続税の計算手順について紹介します。
下記1〜7 の順で計算を行います。
- 遺産総額を計算する
- プラスの財産から課税対象外のものを差し引く
- 課税遺産総額の算出
- 課税遺産総額を法定相続分で按分
- 相続税額を計算する
- 実際の相続割合で按分する
- 基礎控除以外の各種税額控除を適用する
1 遺産総額を計算する
課税対象となる遺産総額を計算します。
課税対象となる遺産に含めるものとしては、以下のものがあります。
- 相続や遺贈によって受け継いだ財産
- みなし相続財産
- 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産
2 プラスの財産から課税対象外のものを差し引く
相続の際にマイナスの財産がある場合は、遺産総額からマイナスの財産を差し引きます。また、マイナスの財産以外にも、下記のようなお金や費用は課税対象とならない財産になるため、差し引くことができます。
- 慈善事業等の公益事業に用いるお金
- 遺体の搬送費用、火葬や埋葬料、納骨料、お布施など、被相続人の葬式にかかった費用
※純金製の仏具の費用等については相続税がかかるものとされています。
3 課税遺産総額の算出
マイナス財産などを差し引いた遺産額の計算ができたら、相続税の基礎控除額を差し引きます。
そして、課税対象となる課税遺産総額を計算します。
計算式は、下記のとおりです。
もし課税遺産総額がゼロもしくはマイナスになる場合は、相続税が課されず、申告は不要となります。そうでない場合には、相続税の申告が必要です。
4 課税遺産総額を法定相続分で按分
課税遺産総額が計算できたら、それを法定相続分に従って取得したものと仮定し、課税遺産総額を法定相続分で按分します。
それぞれの割合は、下記の表のとおりになります。
| 相続人 | 割合 | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 配偶者は1/2 | 子どもが複数いる場合は、1/2を均等に分割 |
| 子どもは1/2 | ||
| 配偶者と両親 | 配偶者は2/3 | 両親が両方健在の場合は、1/3を均等に分割 |
| 両親は1/2 | ||
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者は3/4 | 兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等に分割 |
| 兄弟姉妹は1/4 |
5 相続税額を計算する
4で算出した金額が相続できる金額と仮定し、この金額に対して相続税の税率をかけ、法定相続人別に税額を計算します。
手順としては、法定相続分による取得額が、下記の早見表のどこにあたるかを確認します。そして、取得額に対して、下記表の相続税の税率をかけます。
各相続人の相続税額が算出できたら、それらを合計して相続税の総額を算出します。
相続税率の早見表
| 法定相続分による取得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
また、これらの税率にも控除額が存在します。この控除額は、課税遺産額からではなく算出した相続税額から控除します。
たとえば、相続人Aの課税遺産額が5,500万円、相続人Bの課税遺産額が4,000万円だった場合の相続税額の計算は下記のとおりになります。
| 相続人A | 5,500万円 × 30% − 700万円 = 950万円 |
|---|---|
| 相続人B | 4,000万円 × 20% − 200万円 = 600万円 |
それぞれから算出した税額を合計したものが相続税の総額となります。上記の例の場合、相続税の総額は、1,550万円となります。
6 実際の相続割合で按分する
実際の相続分が上記の法定相続分と異なる場合は、遺言書や遺産分割協議によって決められた実際の相続割合で相続税の総額を按分します。
実際の相続割合は、下記の計算式にあてはめて計算します。
実際の相続額÷課税対象となる遺産総額からマイナスの財産を差し引いた金額=各相続人の相続割合
5 で算出した相続税の総額に、STEP1の相続割合をあてはめ、実際の相続税額を計算します。
1〜6 までの手順に従った計算例
相続財産調査の結果、課税対象となる遺産総額は1億5千万円であった。
負債が3千万円あったため、このマイナスの財産を差し引いた。
式:1億5千万円−3千万円=1億2千万円
基礎控除額を差し引きます。
遺産総額1億2千万円−相続税の基礎控除額3,000万円+(600万円×3人)=課税対象となる遺産総額7,200万円
法定相続分で按分します。
| 配偶者 | 7,200万円×1/2=3,600万円 |
|---|---|
| 各⼦ども | 7,200万円×1/4=1,800万円 |
相続税額の算出
| 配偶者 | 3,600万円×20%−200万円=520万円 |
|---|---|
| 各⼦ども | 1,800万円×15%−50万円=220万円 |
| 相続税額の総額 | 520万円+220万円+220万円=960万円 |
実際の相続割合で計算する
実際に遺言で指定されたそれぞれの相続は下記のようでした。
| 配偶者 | 7,500万円 |
|---|---|
| 各⼦ども | 2,250万円 |
それぞれの相続割合は、
| 配偶者 | 7,500万円÷1億2千万円=0.625 |
|---|---|
| 各⼦ども | 2,250万円÷1億2千万円=0.1875 |
この割合に、先ほど計算した相続税の総額960万円をあてはめて、実際の相続税額を計算します。
| 配偶者 | 960万円× 0.625=600万円 |
|---|---|
| 各⼦ども | 960万円×0.1875=180万円 |
7 基礎控除以外の各種税額控除を適用する
基礎控除以外にも、相続税の負担を軽減するさまざまな控除があります。
これら各種控除は、最後に差し引きます。そして、算出された金額が相続税額となります。
そのため、ステップ6で算出した各相続人の相続税から配偶者控除などの適用可能な税控除を行い、最終的な相続税額を算出することになります。
では、各種税額控除について紹介します。
配偶者の税額控除
配偶者が相続する財産の額が、1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方までは非課税となります。この制度の適用を受けるには相続税の申告が必須となります。
未成年者控除
未成年者控除とは、法定相続人が18歳になっていない未成年者であった場合に下記の計算式で算出された金額が相続税額から控除できる制度です。
例えば、相続開始時に13歳10ヶ⽉の未成年者の場合、(18歳−13歳)×10 万円=50万円の控除となります。
また、もし相続税額よりも控除額が大きかった場合、残りの控除額はその未成年者の扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
未成年者控除については、相続税額が0円になる場合、申告は不要になります。
障害者控除
障害者控除は、相続人が85歳未満の障害者であった場合、下記の計算式により算出した金額を相続税額から控除できる制度のことです。
また、相続人が一般障害者の場合と特別障害者(身体障害者1・2 級の方など)の場合で計算式が異なります。
相続人が一般障害者の場合
85歳 − 相続時の年齢(1年未満切り捨て)×10万円 = 控除額
相続人が特別障害者の場合
85歳 − 相続時の年齢(1年未満切り捨て)×20万円 = 控除額
相続税額よりも控除額が大きかった場合、残りの控除額をその障害者の扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
障害者控除については、相続税額が0円になる場合、申告は不要になります。
⼩規模宅地等の特例
居住用宅地や事業用地について、一定の条件を満たすと最大80%まで評価額を減額できます。これにより、土地の評価額が大幅に下がり、相続税の負担が軽くなります。
⼩規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅として使っていた土地や、事業用に使っていた土地等について、一定の面積まで相続税評価額を減額できる制度です。この制度は、税額控除のための制度ではなく、相続財産の価額を引き下げる制度になります。この制度により、土地の評価額を最大80%まで減額できます。
下記表に減額割合を記載しています。
| 宅地の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 被相続人の事業用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用宅地 | ① 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% | |
| 貸付事業用の宅地 | 一定の法人に貸し付けられた、法人用の宅地 | ②特定同族会社事業用宅地 | 400㎡ | 80% | |
| ③貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | |||
| 一定の法人に貸し出された、 法人の貸付事業用の宅地 | ③貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | ||
| 被相続人などの貸付事業用の宅地 | ③貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | ||
| 被相続人の居住用の宅地 | ④特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% | ||
不動産の相続税に関する計算方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

相次相続控除
相次相続控除とは、10年以内に相次いで相続が発生し、相続税が課税されることになった場合に一定の金額を控除できる制度のことです。
これは、相続人の税負担が過重になるのを軽減する特例になります。
この控除では、一次相続により納めた相続税のうち、1年につき10%の割合で減らしていった金額を二次相続の相続税から控除することができます。
相次相続控除が受けられる条件は以下のとおりです。
- 被相続人の相続人であること
- 前回の相続から今回の相続開始まで10年以内であること
- 前回の相続で、今回の被相続人が相続財産を取得して相続税が課税されていること
弁護士に相談すべき理由とタイミング
相続税の申告は税理士の業務というイメージがありますが、法律問題がからむ場合には弁護士への相談も重要です。以下のような場合には、弁護士への依頼が有効になります。
1 遺産分割協議がまとまらない
相続人間での意見の対立がある場合、遺産分割協議が進まなくなります。法的交渉や調停、審判などへの対応は弁護士の領域となります。
2 特別受益・寄与分の争い
生前贈与や同居介護などがあると、相続分の修正が求められます。相続に詳しい弁護士は、法的主張の裏付けと交渉を依頼者の方に代わって行うことができます。
3 税理士との連携
相続税の申告には税理士、紛争解決には弁護士と、それぞれの専門家が必要となります。双方が連携することで、法務と税務の両面から抜け漏れのない対応が可能となります。
相続でお悩みの場合は弁護士法人シーライトまでご相談ください
相続税の基礎控除額は、相続税が発生するか否かを計算するうえで大切な基準になります。単なる「税金の話」にとどまらず、相続全体の設計・方針に深くかかわる要素でもあります。
そのためにも、基礎控除の正確な理解に加え、事前の財産把握、相続人の確認、控除制度の活用が欠かせません。そして何より複雑な法的・税務的問題が絡む場面では、弁護士への早めの相談が確実な対策となります。
弁護士であれば、ご依頼者の方に代わって相続財産の調査を行うことが可能です。また、さまざまな控除について、適用可能かを検討することもできます。
他の相続人と、遺産について揉めている場合にも、弁護士はご依頼人に代わって、交渉を行い、精神的な負担を軽減することができます。
相続税問題を含め、相続についてお悩みがある場合には、弁護士法人シーライトにご相談ください。