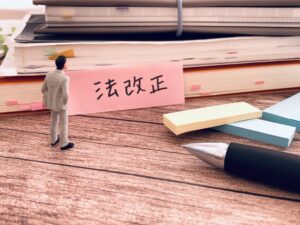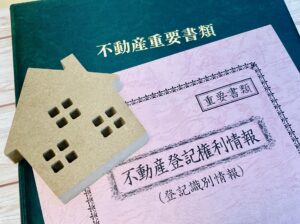遺産相続は、親族間であっても繊細な問題が絡むことが多いため、感情的な対立やトラブルに発展してしまうケースもあります。
トラブルになるケースの中には、相続人の一部の人が、相続人や受遺者(遺言で指定された人)である本人の知らぬ間に、相続の手続が進められていた場合などがあります。 たとえば、叔母が被相続人の銀行預金を引き出していたケース、兄が不動産を勝手に売却していたケースや知らぬ間に遺産分割協議が行われていたケースなどがあり、決して珍しいことではありません。
しかし、「勝手に手続された」と思ったときに、感情的に相手を責めたり、逆に泣き寝入りしたりするのではなく、まずは事実と法的な立場を整理し、冷静に対処することが大切です。今回は、遺産相続で勝手に手続をされてしまった場合について、ケースを交えながらご紹介します。
相続トラブルに直面している方や将来に備えたい方は、ぜひ最後までお読みいただければと思います。
遺産相続の勝手な手続は有効なのか?
相続に関して適切な手続を経ていない一部の人による勝手な遺産の処分や相続は無効となる可能性が高いです。被相続人が亡くなった後は、その被相続人の遺産をどのように分割していくのかを決定する必要があります。
有効な遺言書が存在し、その遺言書の中で全ての遺産について分割方法が記載されている場合は、他に分割するものがないので、遺産分割協議をせずに相続手続を進められます。
しかし、特にそういった遺言書がなく、複数人の相続人が存在するような場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要となります。
遺産分割協議で決定した内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の署名と押印をします。押印は、登録済みの印鑑(実印)で押印し、全員の印鑑登録証明書を添付します。
これをもって初めて、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの各種手続が可能となるため、相続人全員での遺産分割協議が成立する前の勝手な遺産の処分や相続は、無効となるのです。
勝手に相続手続をされてしまった場合には、ケースごとに対処法がありますので、詳しく後述していきます。
遺産分割は原則「全員の合意」が必要
民法において、被相続人が死亡した時点で、相続人はその財産を全員で共有することになります(民法898条)。
しかし、有効な遺言書が存在し、そこに遺産分割の全てが明記されていない限り、各相続人がどの財産を取得するかについては、決まっていない状態となります。
そのため、具体的に財産を分けるには、相続人と受遺者の全員による遺産分割協議が必要です。
この協議で合意が成立しなければ、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることになります。
つまり、相続人の一部が、勝手に特定の財産を取得・処分した場合、それは法的に無効となる可能性が高いです。
勝手に相続されてしまった場合のケース別対処法
相続を巡る「勝手な手続」はさまざまな形で現れます。
ここでは代表的な6つのケースについて、実際に起こり得る状況と法的な対応方法を詳述します。
①遺言書を開示せずに手続された
被相続人が自筆証書遺言を遺していたにも関わらず、その遺言書を保管していた長男が、他の相続人や受遺者に内容を開示せず、相続財産を取り込んでしまい、長男にとって有利な相続手続を進めた。
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要であり、検認を経ずに手続を進めるのは法的に問題があります。
また、遺言を隠した場合には、相続欠格事由(民法891条)に該当することもあります。
- 次に掲げる者は、相続人となることができない。故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
- 相続財産調査を行う
相続財産がどれだけあるのか調査し、その内容を把握します。勝手に相続手続が行われていた場合には、他に財産を隠している可能性もあるため、しっかりと財産調査をすることをおすすめします。 - 話し合いによる解決を目指す
財産調査を行い、特定の相続人による勝手な相続手続が進められていると明確になった場合、話し合いによる解決が可能であれば、話し合いを進めます。
そして、話し合いが成立した場合には、勝手に行われた手続を取り消したり、使い込んだ分を返してもらうなどしたりします。 - 裁判の利用
残念ながら話し合いによる解決が難しい場合には、裁判による手続を進めていきます。
裁判では、財産を取り込んでいる相手に問題がある場合でも、無効な手続の取り消しなどの権利を主張する側に立証責任があります。そのため、訴えた側が充分な証拠を用意する必要があります。
②自分以外の相続人だけで遺産分割協議が行われていた
法定相続人もしくは、受遺者である自分だけが除外され、残りの相続人で遺産分割協議が行われていた。
※受遺者とは、遺言で遺産の贈与を受け取る者として指定された人のことです。この受遺者は、法定相続人だけでなく、たとえば第三者なども指定することができます。
遺産分割協議は、法定相続人、包括受遺者を含め全員で行わなければいけません。それにも関わらず、一部の人だけが除外された状態で行われた遺産分割協議は、無効となります。
包括受遺者が、遺産分割協議に参加するケースとしては、遺言書の中で、遺産の割合だけが指定されており、具体的に何を遺贈するかについて明記されていない場合などは、何を遺贈するのかについて協議が必要となります。
または、遺言書とは異なる方法で遺産を分割することに全員が同意している場合には、包括受遺者も含めて遺産分割協議を行います。
- 話し合いによる解決を目指す
最初に行われた遺産分割協議は無効であるため、改めて遺産分割協議に参加する必要がある全員により、協議をやり直す必要があります。
そのためにまずは、話し合いによる解決を目指します。
相手方に、遺産分割協議が無効であることを伝え、改めて遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。 - 遺産分割協議無効確認訴訟による解決
1の全員での話し合いが、難しい場合には、一部の共同相続人を除外して行った遺産分割協議が無効であることの遺産分割協議無効確認訴訟を提起する方法が考えられます。
これは、遺産分割協議がもめたときの遺産分割審判とは異なるものになります。
勝手に遺産分割協議をされていた場合の注意点
このように遺産分割協議を勝手にされていた場合、相続権を侵害されているので、相続回復請求権を行使することが可能です。
相続回復請求権とは、相続権を有する相続人(このケースでは、遺産分割協議を除外された人)が、相続人であると称して相続人の権利を侵害している者(このケースでは、除外された相続人を無視して手続を進めた他の相続人が単独の権利者であるかのように相続財産を占有等している場合)に対して、相続財産の占有・支配の回復を請求する権利になります。
この行使によって、遺産分割協議によりすでに遺産を分割されてしまった後でも、自身への相続財産を求めることが可能です。
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しない時は、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過した時も、同様とする。
しかし、ここで相続回復請求権には消滅時効があることに注意が必要です。
相続回復請求権の消滅時効は、
- 相続権を侵害された事実を知った時から5年
- 侵害を知らなかったとしても、相続開始の時から20年
を過ぎると権利を行使できなくなるため、遺産を受け取れなくなります。
ただし、悪意があった場合(このケースでは相続権の侵害があると知りながら、一部の相続人を故意に遺産分割協議に呼ばなかった場合)は、時効に関係なく、遺産分割協議によって解決すべきと解釈されています。
③特定の人物により勝手に預貯金が引き出されていた
被相続人の死亡後、間もなく特定の人物が銀行に出向き、被相続人名義の預金を勝手に引き出していた。
遺産分割が完了していない状態で、他の相続人に知らせることもなく、勝手に相続財産に属する預貯金を引き出すことは、他の相続人の権利を侵害する行為です。
- 金融機関へ被相続人の口座凍結を連絡と取引明細の確認
金融機関の口座凍結がまだの場合には、金融機関へ被相続人の死亡を連絡し、口座凍結を行います。こうすることで、以降の引き出しを阻止することができます。
遺産分割協議が成立し、必要書類が揃えば、凍結解除をすることができます。口座凍結をした後は、どの時期に誰が預金を引き出したかを確認します。 - 話し合いによる解決を目指す
遺産分割協議により解決することになります。勝手に引き出してしまった分について、その相続人の取得分を減らし、遺産分割をすることで公平になるようにします。 - 調停や裁判等による解決
話し合いの結果、使い込んだ分についての返還には応じてもらえたものの、遺産分割協議で合意できない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停は、裁判所の調停委員を交えて、相続人同士で話し合いによる解決を目指す方法です。
遺産分割調停でも解決できない場合には、遺産分割審判の手続に移動し、裁判官が遺産分割方法を決定します。
預金の無断引き出しに対して、返還に応じてもらえない場合には、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求による手続を、簡易裁判所または地方裁判所で進めることになります。
不当利得返還請求とは、自分が受け取れるはずだった利益や資産を誰かに不当に使われてしまった場合、これを返還するように請求することです。
不法行為に基づく損害賠償請求とは、他の相続人の故意または過失による行為によって損害を受けた場合、その相手に対して賠償を請求することをいいます。
不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行う場合の注意点
預貯金が使い込まれた場合の不当利得返還請求や不法行為にもとづく損害賠償請求には時効があります。
不当利得返還請求の時効
- 請求できることを知ってから5年
- 請求できるときから10年
上記のいずれか早く経過する期間で時効が成立します。
不法行為にもとづく損害賠償請求の時効
債権法の改正により不法行為にもとづく損害賠償請求時効についても改正がなされました。旧法では、以下のようになっていました。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
改正後では、不法行為による損害賠償請求権が消滅する時効期間は以下の2種類になりました。
- 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
- 不法行為の時から20年間行使しないとき
民法改正前は、不法行為の時から20年という期間制限の法的性質が 条文上明らかでなかったため、この20年間の期間を除斥期間としていました。
しかし、民法改正により不法行為の時から20年という期間制限の法的性質を消滅時効であるとされました。
除斥期間は、時効の中断・停止が認められませんでしたが、改正後は消滅時効とされたことで、中断・停止による延長が可能になりました。
時効を止めるためには、時効が来る前に、配達証明付き内容証明郵便で相手に通知します。
④勝手に不動産を処分されたケースや勝手に相続登記の手続が行われたケース
不動産の所有権移転登記を行う場合には、遺言書や遺産分割協議書などを提出して、不動産の権利が移ったことを証明する必要があります。
そのため、相続人の1人が、他の相続人の同意なく、勝手に不動産を自分名義に変更するケースというのは、起こりづらいといえます。
しかし、遺言書や遺産分割協議書を偽造することで、自分名義に変更している可能性はあります。
また、一部の相続人を除外した遺産分割協議により、不動産の所有権移転登記がなされていたケースというのも考えられます。
遺言書や遺産分割協議書を偽造した場合、不動産登記は形式上完了したとしても、これは犯罪行為であり、刑事責任が問われうる行為です。
自分を除外して行われた遺産分割協議による不動産の処分がなされた場合は、遺産分割協議が無効になることにより、不動産の所有権移転登記も無効となります。しかし、第三者への所有権移転がすでに行われていた場合には、その第三者が保護される可能性があります。
- 抹消登記請求
法務局で、抹消登記手続を行い、勝手に行われた相続登記を無効にします。
その後、遺産分割協議により改めて不動産をどのように遺産分割するか決定します。遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停によって解決を目指します。
しかし、そもそも相手方と争いがある場合には、訴訟(裁判)によって、抹消登記手続請求をする方法をとることになります。 - 偽造書類の刑事責任追及
同意なく、不動産を勝手に特定の相続人だけのものとして相続登記していた場合には、遺言書や遺産分割協議書の文書偽造罪などが成立する可能性もあります。その場合には、民事だけでなく刑事責任の追及も可能です。
⑤勝手に株式を売却された
遺産である株式を他の相続人が勝手に売却してしまったケースとして、相続人が被相続人のオンライン証券口座のパスワードなど、株式売却に必要な情報を知っていた場合、被相続人の死亡後に株式を売却し、被相続人の金融機関口座から売却金を引き出していた例などが考えられます。
本来ならば、株式がどのように分割されるのか決定されていない場合には、株式は相続人全員の共有財産になります。
そして、共有財産を一部の人間により勝手に売却することは許されません。
- 証券会社へ相続開始の連絡を行う
証券会社に相続開始の手続の連絡をします。また、相続開始後の株式の取引履歴を調べ、どの株式が売却されているのかを調べます。 - 話し合いによる解決を目指す
一部の人間による株式の売却によって遺産価値が目減りしたなどの損害を受けた相続人は、その分を考慮した遺産分割協議を行うことで、解決を目指します。 - 裁判による解決
相続人が遺産分割に応じない場合には、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求を検討します。
もし、株式を売却し現金化され、使い込みが発覚した場合も、勝手に株式を売約し使い込みを行った相続人に対しては、使い込みをした金額分を差し引いた遺産分割を行う、話し合いで揉めている場合には、裁判によって不当利得返還請求を行う方法で解決します。
⑥勝手に相続放棄の手続をされた
共同相続人により勝手に自身の相続放棄の手続がなされていたケースもあります。
このようなことが起きるのは、他の相続人の遺産の取り分を増やすために、本人の知らぬ間に相続放棄の手続がされるというケースです。
他の相続人によって、偽造の相続放棄の申述が作成され、家庭裁判所へ勝手に提出されていたということは、今後の話し合いを試みた場合に揉める可能性も高いでしょう。そのため、弁護士に相談することがトラブルを回避する手段となります。
相続放棄の無効を主張
勝手に相続放棄の手続をされてしまった場合には、その相続放棄を無かったことにするための特別の手続は特にありません。
本人の知らぬ間に手続されてしまった相続放棄は、家庭裁判所に受理されたとしても、それは申述があったことの公証に過ぎません。
そのため、相続放棄が無効であることを主張し続ける以外、特に必要な手続などははありません。
遺産相続で勝手に手続をされていると感じた場合に取るべき行動
勝手に手続を進められていると感じた場合には、できる限り早期に対処することが、大切です。
・金融機関や証券会社に相続開始を連絡する
被相続人の財産の使い込みが疑われる場合には、銀行や証券会社に相続開始の連絡をし、口座を凍結するなどの手続を行います。
こうすることで、他の相続人による更なる使い込みを阻止することができます。
・証拠の収集を行う
預金の引き出し、不動産の相続登記の手続などが勝手に行われていると疑われる場合には、どの程度使い込みがあるのかを調べるために、相続人としての立場で取引履歴の開示を求め、預金通帳の取引履歴や不動産登記簿の写しなどを収集します。
・弁護士への早期相談
相続人のあなたを除外して、遺産分割を進めている場合、相続人と知っていて故意に除外されている可能性もあります。
そのようなケースでは、当人同士での話し合いによる解決は難しいこともあり、そういった場合には、弁護士へ早めの相談をおすすめします。
弁護士に依頼することで、どのような証拠を揃える必要があるのかなど、戦略的な対応を整え、ご自身の財産をしっかりと守ることができます。
必要に応じて、不当利得返還請求、損害賠償請求などの訴訟により相手方と裁判で決着をつけることもありますが、そのようなケースでも弁護士が、ご本人に代わって対応していきます。
またもし、相手方が、悪意なく勝手に相続の手続をしていた場合には、話し合いによる解決を目指していきます。そのような場合には、使い込んでしまった分を返還してもらうなどの幾つかの方法で解決をします。
ご自身で話し合いを行うことが不安な場合には、弁護士に依頼することで、ご自身の代理人として弁護士が話し合いを進めていくことができます。弁護士は、円滑に解決できる方法を提案し、スムーズな解決を目指すことが可能です。
話し合いで解決できない場合には、遺産分割調停や遺産分割審判により解決を目指すことになります。そういった場合にも、弁護士は、提出する書面や資料を正確に準備し、感情論ではなく法的根拠に基づいて一貫した主張をすることができるので、依頼者の方にとって有利な結果を得ることが可能です。
弁護士への相談が有効なケースとは?
下記のようなケースでは、特に弁護士への相談が有効なケースと言えます。
- 相手方が財産を独占しようとしている
- 自分だけでは証拠収集や交渉が難しい
- 裁判所への対応が必要
このような場合には、弁護士に相談することで法的に整ったアプローチが可能となります。
特に相手との関係がこじれているときや、相続財産の金額が大きい場合には、感情的対立を防ぎつつ冷静に権利を主張するためにも、専門家の関与が不可欠となります。
遺産相続の時効に注意
勝手に遺産相続の手続をされた場合に、その遺産相続の手続は無効となります。改めて遺産分割協議を行う場合、その遺産分割協議自体には、時効はありません。ですから、いつでも遺産分割協議のやり直しができます。
しかし、請求できる権利には時効が設けられており、その期限を過ぎると権利が消滅してしまいます。
前述しているそれぞれの権利の時効についてまとめていきます。
不当利得請求や不法行為にもとづく損害賠償請求には時効がある
| 権利 | 消滅時効 |
| 不当利得返還請求(民法第166条) | 以下の早い方の時点で時効が成立 ❶請求できることを知ってから5年 ❷請求できるときから10年 |
| 不法行為による損害賠償請求(民法第724条) | 以下の早い方の時点で時効が成立 ❶損害および加害者を知った時から3年 ❷不法行為のときから20年※1 |
※1 この20年間の期間は、民法改正前までは、除斥期間とされ中断・停止が認められませんでした。しかし、民法改正後、この20年間は、消滅時効として明記され、中断・停止による延長が可能になりました。
そのため、遺産分割のやり直しを希望する場合には、早めに相手に通知して行動を起こすことが大切です。時効を止めるには、時効前に請求をすることが必要です。
時効前に請求をしているという証拠を残すためにも、相手への通知は、到着した日付が分かるように配達証明付き内容証明郵便で請求を行うことが大切です。
また、相続に関係する、特別受益や寄与分の主張、遺留分侵害額請求、相続税の申告や相続放棄の手続などにも時効があるため注意が必要です。
期限のある相続に関係する手続の一覧
期限がある主な手続は、下記のとおりです。
| 3ヶ月以内 | 相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)の選択期限 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 ※1 ※1 期限を過ぎると、無申告加算税と延滞税が課されます。 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告期限と納税 ※2 遺産が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以上の場合 ※2 期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税を支払う必要があります。 |
| 1年以内 (相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから) | 遺留分侵害額請求 ※3 ※3 遺留分権利者が相続開始を知ってから1年間に当てはまる場合でも、相続開始の時から10年が経っているときには、時効によって権利が消滅します。 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 ※4 ※4 相続登記を期限内に行われないと、罰則(10万円以下の過料)の対象となりますが、期限を過ぎても相続登記はできます。 相続税の特例や軽減手続 |
| 5年以内 | 株主の権利 |
| 5年以内/10年以内 | 預金を払い戻しできる権利 |
| 5年10ヶ月以内(相続税の納付期限後5年間) | 相続税還付の期限 |
| 10年以内 | 特別受益と寄与分の主張 ※5 ※5 例外として10年経過した後でも特別受益や寄与分の規定が不適用とならないケースがあります。 |
この相続に関する期限については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
よくある誤解とその対策
- 「相続登記を済ませた者が勝ち」ではない
登記は形式にすぎず、実体的な権利関係がなければ取り消しの対象となります。虚偽の内容に基づいた登記は、後に抹消が認められます。
ただし、虚偽の立証が必要となり、立証が難しい場合には登記の取り消しができないこともあります。 - 「遺言書があれば絶対」は誤解
遺言書に従っても、相続人には最低限の権利(遺留分)が保障されています。また、形式不備があれば遺言自体が無効となることもあります。 - 「話し合いで何とかなる」わけではない
感情的な対立や金銭が絡む場合には、当事者間の話し合いが難航することもあります。冷静かつ法的な枠組みの中で対応することが解決への近道となります。
遺産相続を弁護士に依頼するメリット
遺産相続の手続を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
円滑に手続を進められる
遺産相続では、相続人はさまざまな手続をしなければなりません。
その中には、期限のある手続もあり、期限を迎える前に対応しなければならないものもあります。
手続自体を弁護士に任せることで、弁護士が対応すべき優先順位を整理し、円滑に手続を進めていきます。
相続人本人の負担がかからない
ご自身で相続手続を行うことは、大変な手間が生じます。
他の相続人が勝手に手続を進めた場合には、相続人調査や遺産の調査、遺産分割協議書の作成などの事項だけではなく、無効確認訴訟や遺産分割調停、遺産分割審判にも対応していかなければなりません。
弁護士に任せることで、調停や裁判も任せることができるので、依頼者本人の負担が軽減されます。
状況に応じた適切な対応を行う
他の相続人が勝手に相続手続をしていた場合、遺産分割協議により解決できるもケースもあれれば、裁判が必要になるケースもあります。それぞれの状況に応じて適切な対応をしていく必要があります。
弁護士は、その状況からとるべき行動を判断し、対応していきますので、安心して進めていくことができます。
相続人同士に争いがあっても代わりに対応してもらえる
遺産相続では、相続人同士の争いの発展してしまうケースもあります。
弁護士に依頼することで、あなたの代理人として、相手方と交渉を行います。そのためご自身で対応する必要はありません。また、いざ遺産分割調停や裁判になった場合にも対応することができます。
有利に解決できる可能性が高い
弁護士は、法律の知識を活かし、依頼者の方が最大限の利益を得られるように行動します。その結果、ご自身にとって有利に解決できる可能性が高まります。
遺産相続の手続でお困りの場合は弁護士法人シーライトへご相談ください
勝手に相続手続をされてしまったら、まずは事実の確認と証拠の確保が大切になります。そのうえで、法的に適切な対応を講じることで、ご自身の権利を守ることができます。
相手の行動に違法性があると感じ、話し合いにも応じる姿勢が見られない場合には、法的手段を活用しましょう。
相手方との交渉をどのように進めていけば分からない場合には、相続に詳しい弁護士に相談することで、トラブルを早期に、かつ適切に解決する道が拓けます。
遺産相続の手続でお困りの場合には、弁護士法人シーライトにご相談ください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
相続の話し合いは、ほんの些細なきっかけから揉めてしまうことが意外と多いです。そのような場面で少しでもお力になるべく、初回相談は無料とさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
\初回50分間のご相談が無料/

弁護士法人シーライト
受付時間:平日9時~18時 | 相談時間:平日9時~21時
まだお問い合わせしない場合は
相続コラムが届く LINE友だち 追加がおすすめ!