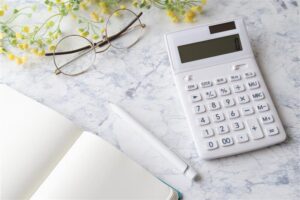高額な遺産相続がもたらす“争族”の現実
相続が開始する前は、相続トラブルは起きるはずがないから大丈夫と思っていても、相続によるトラブルは誰にでも起こり得る問題です。
特に、相続財産が高額な場合、争いが発生すると深刻化しやすく、長期化する傾向があります。
今回は、高額な遺産相続で争いが起きてしまうケースについてご紹介します。
また、どういった場合に弁護士が必要になるのかについても解説します。
高額な遺産相続とは?
高額な遺産相続は、厳密にこの程度の遺産総額と決まっているものではありませんが、相続財産の総額が1億円以上にのぼるケースが多くなります。
遺産の内容としては、以下のような財産について争いが生じる可能性があります。
不動産
都心部など条件の良い立地に位置する場合には、不動産の評価額も土地・建物合わせて1億円以上も珍しくありません。
また、被相続人が居住目的とは別に、収益不動産として賃貸マンションやテナントビル1棟などを所有していたケースも、高額な遺産相続となります。
遺産の中に不動産がある場合には、不動産の分割方法や評価額について相続人同士でもめる場合があります。
株式・投資信託などの金融資産
株式には、上場株式や非上場株式があります。高額な遺産争いが発生する場合の株式は、評価額にして数千万円以上になる株式を保有しているケースといえます。
中小企業の自社株を保有する経営者が、突然亡くなった場合には、経営していた会社の株式を相続することになるため、事業承継の問題が発生します。
事業用資産
事業用資産の中には、例えば賃貸用マンション、自社ビル、駐車場、貸店舗、自社店舗などがあります。
それぞれの事業用資産に対し、額面の評価方法はさまざまなものがあり、価値の算定が難しく、相続問題に発展するケースもあります。
美術品・骨董品、宝石・貴金属などの実物資産
これらの資産は、真贋の問題があるため、鑑定書がない場合には、真贋の鑑定が必要となります。
希少なものであれば、その価値は非常に高くなり、高価な遺産となります。
上記の例で挙げたもの以外でも、預貯金などの財産も高額となるケースがあります。
高額な遺産相続で争族が起きる理由
生前贈与
財産が多い場合には、相続税対策の1つとして生前贈与を行っているケースもあります。
たとえば、生前贈与を受け取っていない相続人は、「その生前贈与は、特別受益なのだから、被相続人の遺産に持ち戻すべき」と主張しており、生前贈与を受け取った相続人は「これは特別受益に当たらない」と主張しているケースが考えられます。
このような場合、問題となるのは、生前贈与が特別受益にあたるのかどうかです。
遺贈、婚姻費用の贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与は、特別受益にあたります。そのため、生前贈与が特別受益の対象とされた場合には、その価額を相続財産へ加算したうえで遺産分割を行います。
また、贈与契約は、贈与する側(被相続人)と贈与される側(相続人)の意思の合致により成立するものです。そのため、特に贈与契約書の作成をせず口頭でも成立します。
しかし、契約書を作成せずに金銭や宝石といった動産の贈与がなされた場合、相続発生後に、本当に被相続人の意思に基づく贈与であったのかどうか、相続人が勝手に被相続人の財産を取得しているのではないかといった点で他の相続人とトラブルになることもあります。
もし、生前贈与として認められた場合でも、今度は特別受益にあたるかどうかという点で争いに発展する場合もあります。
特別受益の持ち戻しについては、こちらの記事で紹介しています。

生前贈与と相続の関係については、こちらの記事で紹介しています。

名義預金・名義株の問題
高額な財産を保有している被相続人が生前から、子ども(相続人)名義の預貯金口座を開設し、そこに被相続人の財産を入金しているような場合があります。
その目的は、相続税対策の他に、一定の条件を満たしていれば贈与税対策となるなどの理由があるでしょう。
しかし、一部の相続人から特定の相続人に対して、「相続人名義の預金があるけれど、実際には被相続人の財産が入金されているから、これは被相続人の財産である」と主張される場合があります。
もし、相続人名義である口座の預金通帳や印鑑を被相続人が保管していて、相続人が口座の存在すら知らなかったような場合には、名義預金と判断され被相続人の財産と認定される可能性が高いです。
また、預金だけではなく、株式についても名義株の問題が発生することがあります。
被相続人の経営する会社の株主名簿に相続人が株主として記載されていたものの、実際に出資していたのが被相続人であった場合、被相続人が保有していた名義株であると、他の相続人から指摘されることもあります。
しかし、たとえ被相続人が株式取得に必要な費用を出資していたからといって、すぐに名義株であると決定されるわけではなく、株式の取得代金ないし払込金の出捐者、名義貸与者と名義借用者との関係、名義借りの理由等を総合的に考慮して判断されます。
一部の相続人による遺産隠しや遺産処分の問題
一部の相続人が、被相続人の美術品、骨董品などを勝手に持ち去ってしまう場合や、勝手に売ってしまうようなケースがあります。
相続人が複数いる場合、遺産分割前の遺産については、相続人全員の共有の遺産となっているため、遺産を勝手に持ち去ることや売却等の処分をすることは、他の相続人の権利を侵害することになり、相続人同士のトラブルに発展する場合があります。
例えば、被相続人と同居していた相続人の遺産隠しや使い込みなどが疑われる場合などは、他の相続人が不信感を持ってしまい、話し合いによる解決が難しいケースもあります。
また、美術品などの遺産以外にも、被相続人の預金の無断引き出しなどを行うといったケースもあります。こちらの記事で紹介しています。

遺産の評価額方法についての争い
高額な遺産相続の場合、複数の不動産や株式が含まれていることが多いです。これらの財産は、日々価値が変動する財産であるため、相続が開始されるとどのような評価方法で価額を決定するのか、どの時点を基準にするのかが問題となります。
相続人が遺産分割を行うために、遺産全体の総額を算定しなければなりません。そのためには、日々変動する財産についても評価額を決定する必要があります。
しかし、価額の大きい不動産や株式が相続財産に含まれている場合、その不動産や株式を相続する人と相続しない人の間で評価額についての話し合いがまとまらないこともあります。
不動産の評価方法について
不動産については、遺産分割方法を決定する他に不動産の評価額を決定しなければなりません。その評価額の決定方法には大きく4つの方法があります。
実勢価格、公示価格、相続税評価額(路線価)、固定資産税評価額になります。
遺産分割における不動産の評価額は、実勢価格を参考に合意して決めるのが一般的ですが、相続人全員が合意すればどの評価方法を基準としてもかまいません。
上場株式については公開されている相場がありますが、非上場株式の株価算定には、多様な方法があり、その算定方法は複雑です。
不動産の評価方法については、こちらの記事で紹介しています。

株式の評価方法については、こちらの記事で紹介しています。

話し合いがスムーズに進めば問題ありませんが、どの評価方法を基準とするのか、どの時点を評価額とするのかについて、話し合いがまとまらない場合には、争いへと発展してしまう可能性があります。
遺言が特定の相続人の遺留分を侵害している場合
遺言の内容は、被相続人が自由に自身の財産の処分方法を決めることができるのが原則です。
しかし、法的に有効な遺言が、特定の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を巡って相続人同士がトラブルになる場合があります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を主張している相続人が、遺産を多くもらいすぎている人から、遺留分に相当する金銭を請求する手続です。
例えば、複数いる被相続人の子どものうち、特定の子どもに対しては億単位の高額な遺産を相続させ、それ以外の子どもには、数百万円の遺産を相続させるといった内容の遺言の場合、それに不服な相続人から「遺言は無効である」と主張されることがあります。
しかし、遺言が無効となる要件というのは、厳格な方式を満たしていない書面の場合です。つまり遺言が、特定の相続人の遺留分を侵害している内容であっても、法的に方式を満たしていれば遺言としては問題ないと判断される可能性が高いです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がある普通方式と一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言の4つの種類がある特別方式があります。
船や飛行機のトラブルなどで生命に危機が迫るような緊急事態が発生している状況下での遺言が、特別方式の遺言となり、通常の生活の中で用意される遺言は、普通方式になります。
例えば、自筆証書遺言が無効になるのは、遺言の形式に不備があるケースや第三者からの強要により被相続人の意思に基づかない遺言のケースなどです。
遺言が無効になるケースについては、こちらの記事で紹介しています。

特定の相続人から死因贈与契約の主張がなされている場合
相続開始後、被相続人と相続人との間で、死因贈与契約が交わされていたとの主張がなされることがあります。
死因贈与契約は、遺言のように厳格な要式性はなく、契約書がなくても当事者間の意思表示のみで成立します。
高額な遺産に対して、死因贈与契約があったのかどうかは、他の相続人にも影響が出てくる問題であるため、死因贈与契約成立の可否について争われることもあります。
例えば、被相続人が生前に書いたメモ書きを持ち出して、「これが死因贈与契約を交わした書面である」と相続人から主張がなされるケースなどがあります。
しかし、契約書がないと死因贈与契約を立証しにくいため、相続人が死因贈与契約書であると主張している書面が、被相続人が作成したものであるのか、書面が作成された経緯、書面の内容から死因贈与の趣旨が読み取れるかどうかなど、様々な要素から死因贈与契約が成立するか否かが判断されます。
遺言と死因贈与との違いについては、こちらの記事で紹介しています。

高額な遺産相続で弁護士が必要になる場合は?
相続人同士で感情的な争いが起こりかけている段階で、相続に強い弁護士が介入することで、冷静かつ中立的な話し合いを実現できます。
相続人間での話し合いがまとまらず平行線の場合
名義預金や名義株式が相続財産に含まれるのかどうかなどの遺産の範囲についての争い、遺産の株式や不動産に関する評価額についての争いや、遺言による遺留分侵害に関する争いなど、相続人同士では遺産分割や遺留分について話し合いがまとまらず、感情論ばかりの状況になってしまうような場合には、弁護士に依頼し、他の相続人との交渉を代理することで解決へ向かう可能性が高まります。
例えば、生前贈与が特別受益にあたるか、持ち戻し免除の意思表示があったのかなどを判断するためには、法律的な知識が必要となります。生前贈与の状況に応じて個別に判断していきます。
また、不動産といった評価額が変動する財産を生前贈与された場合には、相続開始時の評価額の算出方法も複雑で、個人で調べ、他の相続人と協議を行うのは非常に大変な作業となります。そういった煩雑な作業も弁護士に依頼することができます。
調停・審判・訴訟への対応が必要な場合
遺産の範囲に関して、遺産分割協議、遺産分割調停で解決できない場合、遺産確認訴訟により遺産の範囲を確定させることになります。
遺産の範囲については合意ができている場合でも、不動産などの高額な遺産の分割方法について合意ができない場合には、遺産分割調停や遺産分割審判により解決することになります。
他の相続人と争いがある場合には、ご自身の主張の根拠となる証拠が必要となります。
寄与分や特別受益についての立証、美術品や不動産などの鑑定結果に基づく評価額の主張、遺留分に関する法的主張など高額な遺産相続におけるトラブルには、さまざまなものがあり法的な知識が必要となります。
相続に詳しい弁護士へ依頼することで、相続人本人に代わって、者人の権利と利益を最大限に守ります。
事業承継をめぐる混乱が起きそうな場合
中小企業の事業を引き継ぐ際、経営者の後継ぎ問題が相続と重なることでトラブルに発展するケースがあります。
例えば、
- 長男が事業承継予定だったが、他の兄弟が株の分配を要求している
- 会社の不動産や機材などが遺産に含まれており、評価額の算定が争点になっている
こういった争いが起きそうな場合やすでに起きている場合には、事業継続の安定性と、法的な平等のバランスが難しく、弁護士など法律の専門家の介入による調整が必要となります。
高額な遺産争族には“予防”と“弁護士の介入”が鍵となります
不動産の共有状態・名義預金・未上場株式などの複雑な財産が、遺産相続に含まれている中で争いがある場合には、税務、登記なども絡み合う問題になるため、相続に強い税理士や司法書士とも提携している弁護士の関与が求められるでしょう。
弁護士は、各相続人の主張を法的に整理したり、証拠収集や財産調査の補助をしたり、相手方との代理交渉を行ったりすることができます。
また、高額な遺産の中には、分割が比較的簡単な現金、預貯金だけではなく、不動産や株式などの分けにくい財産も多数存在することが多いです。
こうした場合、財産の分けにくさそのものが争いの原因となり、その場合、相続税や評価額の問題も複雑化します。
弁護士が相続人間の争いの間に入ることで、感情的対立の回避や抑制をすることができます。そして、争いが長引くことで生じる経済的なコストや心理的な負担の軽減をすることにもつながります。
高額な遺産相続でお困りの場合には、弁護士法人シーライトにご相談ください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
相続の話し合いは、ほんの些細なきっかけから揉めてしまうことが意外と多いです。そのような場面で少しでもお力になるべく、初回相談は無料とさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
\初回50分間のご相談が無料/

弁護士法人シーライト
受付時間:平日9時~18時 | 相談時間:平日9時~21時
まだお問い合わせしない場合は
相続コラムが届く LINE友だち 追加がおすすめ!