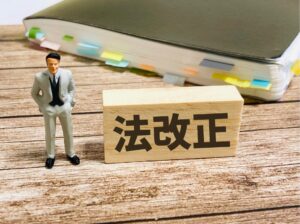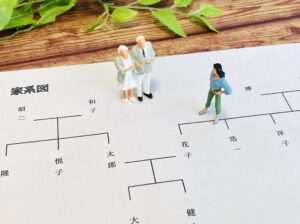被相続人が遺言を残さずに亡くなってしまった場合や、作成された遺言書が無効であった場合には、相続人全員(共同相続人)で遺産分割協議を行うことになります。 遺産分割協議は、被相続人が残した遺産を相続人間で、どのように分けるか話し合いで決定するための大切なプロセスになります。
また法律では、誰が相続人になれるのかという法定相続人について、相続人になることができる人の優先順位や相続できる遺産の分量(法定相続分)について定められています。 この遺産分割協議では、法律で決められている法定相続分などが遺産分割の基本的な指標となりますが、必ず法定相続人の順序や法定相続分に従って遺産分割をしなければいけないのでしょうか?
今回は、遺産分割協議において法定相続分と異なる合意の可否や注意点などについてご紹介します。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法第900条で規定された相続人の相続割合のことです。そして、この法定相続分は、法定相続人になる人と人数、その人の相続順位によって決まります。
たとえば、被相続人が配偶者と子ども2人を残して亡くなった場合、法定相続分は、配偶者が1/2、子どもがそれぞれ1/4(1/2÷2人)ずつとなります。この割合は法律で定められています。
詳しくは、各相続人の相続割合をまとめた下記表を参照ください。
| 相続人 | 法定相続分 | |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1 | |
| 配偶者+子 | 配偶者 | 1/2 |
| 子 | 1/2÷人数 | |
| 子のみ | 1÷人数 | |
| 配偶者+直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
| 直系尊属 | 1/3÷人数 | |
| 直系尊属のみ | 1÷人数 | |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹 | 1/4÷人数 | |
| 兄弟姉妹のみ | 1÷人数 | |
法定相続人について
法定相続分は、法定相続人になる人と人数、その人の相続順位によって決まると述べましたが、では誰が法定相続人になるのかについてもご紹介します。配偶者は、他の法定相続人の順位に関係なく常に法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人に関しては、以下のように相続順位が定められています。
| 常に相続人 | 配偶者 |
|---|---|
| 第1順位 | 子や孫など直系卑属 |
| 第2順位 | 親や祖父母など直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
もし、被相続人が亡くなる以前に、相続人である被相続人の子どもや被相続人の兄弟姉妹も既に亡くなっていた場合には、その子ども(つまり被相続人から見て孫や甥姪にあたる人)が、代襲相続の制度により、相続人となります。法定相続人の考え方としては、相続順位の高い人がいる場合には、それより下の順位の人は、相続人になれません。
法定相続分と異なる合意は可能か?
法定相続分は、遺産分割協議の際に指標として使われますが、遺産を必ずしもその通りに分けなければいけないわけではありません。法定相続分はあくまで基準であり、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。
では、法定相続分とは異なる遺産分割が行われるケースをあげてみます。
ケース1:特定の相続人が特定の財産を引き継ぐ場合
たとえば、実家の家屋を被相続人の子どもである長男が引き継ぎ、他の子どもは、現金や預金を相続するといったケースが考えられます。
このような遺産分割は、家屋を売却する手間や費用を省くために合理的とされる場合があります。
ケース2:全員が納得する特別な事情がある場合
共同相続人が話し合いの中で、特定の財産を誰かが引き継ぐ方が現実的である、または公平であると感じる特別な事情がある場合などには、法定相続分と異なる分配が行われるケースもあります。たとえば、遺産の中で、売却することが難しい不動産が多くの割合を占めているケースでは、その不動産を特定の相続人に取得させると、他の相続人の取得額が相続分より少なくなるといった場合もあります。代償分割によって、不動産を取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う方法もありますが、その相続人に代償金を支払う財力がない場合には、相続人全員が合意のうえで、法定相続分とは違う遺産分割をすることになります。
他にも、夫が亡くなり妻と未成年の子どもが相続人になった場合、残された妻の今後の生活も考慮して、とりあえず妻が遺産の全てを相続するというケースもあるでしょう。この場合は、配偶者100%、子どもが0%という割合で遺産を分割したということになります。これは、各相続人のおかれている生活状況などの事情を考慮して、法定相続分にとらわれない割合で分割が行われたと考えられます。
相続財産に債務がある場合の注意点
相続が発生すると、遺産にはプラスの財産(現金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払いの医療費、保証債務など)も含まれます。もし遺産の中に、債務も含まれている場合には、当然債務も相続することになります。遺言がない場合や遺言書が無効の場合には、相続人たちは法律に従い、遺産を分割して承継します。
債務の相続に関する基本ルール
遺言書がない場合、債務もプラスの財産と同様に、法定相続分に基づいて分割することもできますし、遺産分割協議の話し合いの中で、相続債務の承継者や承継割合を決定することもできます。たとえば、債務を特定の相続人がすべて引き受ける代わりに、現金や不動産などのプラスの財産を多く受け取るといった方法も可能です。ただし、債務に関しても、法定相続分と異なる分割を行う場合には、遺産分割協議で相続人全員が同意することが不可欠です。1人でも同意しない相続人がいる場合、合意は成立せず、法定相続分に基づく分割や家庭裁判所での調停が必要になります。
債権者の立場
債務について、法定相続分とは異なる相続分となったとしても、被相続人の債権者がその遺産分割協議の内容を知っているかどうかは分かりません。そのため、法定相続分とは異なる相続分となったケースにおける相続債務の取り扱いについては、債権者は、遺産分割協議で決定した内容にかかわらず、法定相続分に従い、各相続人に対して債務の支払いを請求できます。もし法定相続分と異なる分割を行いたい場合には、個別に債権者の同意をとることが必要となります。
遺産分割協議における注意点
遺産分割協議が成立した場合、その内容を遺産分割協議書に記録する必要があります。遺産分割協議書とは、話し合いで決まった結果を正式にまとめた書類になります。法的効力のある書類になるため、記入漏れやミスがないように作成しなければなりません。たとえば、この遺産分割協議書は、相続登記や税務申告にも使用されるので、正確かつ明確に記載することが求められます。
遺産分割協議においてトラブルを防ぐために
法定相続分と異なる分割を行う際には、相続人間の意見の相違や感情的な対立が起きやすくなります。このようなトラブルを防ぐためには、以下のポイントを押さえておくことも大切になります。
① 相続人全員の納得を得る
相続人全員が協議内容に納得し、署名・押印を行うことが不可欠です。
② 公平性の確保
特定の相続人に有利すぎる内容にならないよう、公平性を考慮した分割を心がけることが大切です。
③ 専門家の活用
遺産分割協議は法律や税務に関わる複雑な問題が絡むことが多いため、弁護士などの専門家に相談することでトラブルに発展することを防ぐことができます。
遺産分割調停・審判
相続人間の遺産分割協議で分割方法が決まらない場合には、家庭裁判所による遺産分割調停、審判の請求をすることができます。家庭裁判所での遺産分割調停は、話し合いによる解決になるため、相続人全員が合意するならば、法定相続分ではない別の遺産分割方法で調停条項を作成することは可能です。遺産分割審判の場合には、法定相続分を基本とした分割が行われることが多くなります。
弁護士へ依頼するメリット
遺産分割協議は、法律や税務、感情的な側面が絡む複雑な手続となる場合があります。弁護士へ依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
法律的なアドバイスを得られる
弁護士は、遺産分割協議が法的に有効であるか、または将来的な紛争を防ぐための方法をアドバイスすることが可能です。
相続人間の調整
感情的な対立が生じた場合、弁護士が第三者として介入することで、冷静かつ客観的な話し合いが進められ、スムーズな遺産分割協議を実現する可能性が高まります。
書類作成のサポート
遺産分割協議書は法的な効力があり、財産を正式に相続するために金融機関や証券会社から提出を求められる重要な書類です。弁護士が、遺産分割協議書の作成をすることで、書類を作成する労力も不要になるだけではなく、その後の手続もスムーズに進めることができます。
遺産分割協議について弁護士に依頼するメリットについては、こちらの記事でも紹介しています。

まとめ
遺産分割協議では、法定相続分と異なる内容で合意することが可能となりますが、そのためには、相続人全員の同意が必要となります。また、法律や税務の観点で注意すべき点が多いため、弁護士などの専門家に相談することも必要になるケースがあります。遺産分割協議でトラブルを避け、円滑に手続を進めていきたい場合には、相続に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士は、法的な助言だけではなく、感情的な衝突の調整や書類作成のサポートを通じて、相続人全員が納得できる解決策を提供し、スムーズな遺産分割協議の実現を目指します。
相続に関する悩みを抱えている方は、弁護士法人シーライトにお問い合わせください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
相続の話し合いは、ほんの些細なきっかけから揉めてしまうことが意外と多いです。そのような場面で少しでもお力になるべく、初回相談は無料とさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
\初回50分間のご相談が無料/

弁護士法人シーライト
受付時間:平日9時~18時 | 相談時間:平日9時~21時
※まだお問い合わせしない場合 LINE友だち 追加がおすすめ!