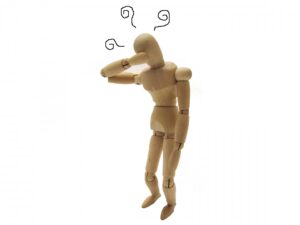近年、老後資金や資産運用の一環として、投資信託を保有する人が増加しています。その結果、被相続人の遺産に投資信託が含まれるケースも珍しくありません。
しかし、投資信託は現金や預貯金とは異なる特徴を持ち、相続手続において相続人同士のトラブルに発展する要因となることもあります。
「投資信託は相続できるのか?」「相続人の一部の人が勝手に解約できるのか?」「評価額が日々変わる中、どのように分ければ公平なのか?」といった疑問に直面するご遺族も少なくないと思います。
今回は、投資信託の仕組みから、相続開始後の具体的な手続などについて解説します。
投資信託の仕組みと相続財産としての位置づけ
①投資信託とは?
投資信託(ファンド)とは、投資家から集めた資金をひとつにまとめ、運用会社が株式や債券、不動産などに投資し、運用していく金融商品になります。
投資信託は、信託契約に基づいて成立するものであり、投資家は、受益者として信託財産の運用成果を受け取る立場です。
仕組み上、投資信託には主に以下の関係者が関与します。
- 運用会社(委託者):資金の運用方針を決定・指示
- 信託銀行(受託者):実際に資産を保有・管理
- 販売会社(証券会社・銀行等):投資信託の販売・解約手続の窓口
- 受益者(投資家):投資信託の保有者
投資信託は、「信託受益権」という権利として保有する形式になっており、これは法律上の分類では「無体財産権」にあたります。そのため、現金や不動産と同様に、相続財産の一部として扱われます。
②投資信託は遺産として引き継げるのか?
投資信託は、相続可能な財産です。正しくは、投資信託の信託受益権という権利が相続の対象になります。
この信託受益権が、預貯金や不動産と同様に遺産分割の対象となります。 ただし、次のような特徴に注意が必要です。
- 受益権には名義人が存在するため、相続後は名義変更または解約の手続が必要
- 投資信託の価値は日々変動するため、相続評価や分割時にトラブルが生じやすい
③相続財産としての評価方法
投資信託の価額は市場の動向によって日々変動しています。
そのため遺産分割の内容について合意に至った時点と、実際に遺産分割により財産を承継する時点で、投資信託の受益権の価値が大きく異なっている場合もあります。
投資信託の受益権の価値をどの時点にするのかについては、相続人間で自由に決定することが可能です。
比較的多いのは、相続開始日(被相続人の死亡日)の基準価額(純資産価値)を投資信託の評価額とするケースです。
基準価額を調べる方法としては、金融機関からの資料請求で確認が可能です。
投資信託の相続手続の流れ
投資信託が遺産に含まれている場合、他の財産と同様に相続手続を進める必要があります。
ただし、金融商品としての特殊性があるため、各段階での注意が必要です。
①投資信託の相続手続の基本的な流れ
1.死亡届の提出と戸籍収集
市区町村に死亡届を提出し、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本を取得します。
2.相続人の確定
取得した戸籍から、法定相続人を確認します。
3.相続財産の調査
投資信託では、銀行、証券会社、信託銀行などから運用報告書や取引残高報告書といった書類が送られてくることがあるため、被相続人の遺品を確認します。
また、オンラインで行うタイプの投資信託では、メールで関連書類が送られてくるため被相続人のメールを確認する必要があります。
これらの方法では探索が難しくヒントがないという場合は、証券保管振替機構に情報開示請求を行い、故人名義の口座が保有されている証券会社がないかを確認する必要があります。
4.金融機関での名義変更・換金手続
証券会社等に連絡し、必要書類を揃えて手続を行います。詳細は後述します。
5.遺言書の有無の確認
公正証書遺言がある場合はその内容に従い、自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所での検認手続が必要となります。
6.遺産分割協議(遺言がない場合)
相続人全員で話し合い、どの資産を誰が相続するかを決定します。
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られた場合、遺産分割協議書を作成し、署名・実印押印・印鑑証明書添付します。
ちなみに遺産分割協議書を作成する際、投資信託の受益権を誰が相続するのか、あるいはどのような割合で相続するのかを明記します。そして、投資信託の受益権の価値をいつの時点を基準として算定したのかということも明記しておくことで、後に相続人間で揉めることを防ぐことができます。
7.遺産分割調停・審判(遺産分割協議がまとまらなかった場合)
遺産分割協議で話がまとまらず、合意に至らなかった場合、遺産分割調停を行います。
調停手続では、調停委員が事情を聴き助言や解決案を提示します。相続人全員の合意が得られれば、遺産分割調停が成立し、遺産分割は終了します。
調停で合意に至らなかった場合、審判手続に移行することになります。
審判手続では、裁判官が遺産に属する物や権利の種類及び性質などの事情を考慮して審判をします。
8.相続税申告・納付
相続税が発生する場合は、原則として相続開始から10ヶ月以内に申告・納付が必要となります。
②金融機関での手続の概要
投資信託を相続するときの金融機関での名義変更の手順について解説します。
金融機関に被相続人の死亡を連絡
被相続人が取引をしていた証券会社などの金融機関に、被相続人が死亡したことを報告します。
これは、遺産分割協議で遺産分割が未決定の状態であっても速やかに行う必要があります。
被相続人の死亡連絡を受けた段階で、金融機関は、被相続人口座をいったん凍結します。口座を凍結することで、不正な引き出しを防ぐことができます。
それ以降は、遺産分割が完了するまでの間、原則として投資信託の受益権を処分することができなくなります。
投資信託の相続方法の確定
有効な遺言書がある場合には、遺言どおりに相続します。ただし、その遺言により相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額の支払いを請求することができます。
遺言書がない場合は、遺産分割協議で誰が投資信託を相続するのか確定します。
遺産分割協議を行う際、遺産の分割方法は、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つに分類されます。
現物分割とは、投資信託や不動産などの財産を相続人にそれぞれに振り分けて分割する方法です。代償分割とは、投資信託を相続する人を定め、相続しない相続人に対して代償金を支払う分割方法です。
換価分割とは、遺産を売却し、得られた売却金を法定相続人の間で分配する方法です。
共有分割とは、遺産の全部又は一部を複数の相続人が共有で相続する方法です。
しかし、投資信託に関しては、金融機関の手続上、換価分割を行うことができません。
なぜなら、被相続人が死亡すると口座が凍結されるため、被相続人が所有する投資信託を売却して現金化することができないためです。
被相続人が所有する投資信託を現金化できるのは、名義変更手続の完了後、相続人の口座へ移管されてからとなります。
ただし、被相続人名義での換価分割はできませんが、名義変更後に相続人の1人が換金して他の相続人に分配するという実質的な換価分割は可能です。
したがって、まず代表者となる相続人を1人決め、当該相続人の口座に投資信託を移動させます。その後、その相続人が、投資信託を売却し現金化したものを他の相続人へ分配する形を採ることになります。
また、投資信託の共有分割は、おすすめできません。
投資信託の受益権を共有状態のままにした場合、売却や解約、移管などの手続には全員の同意が都度必要になるため、極めて非効率となります。
また、共有状態にすることは、相続後も継続的なトラブルリスクがあります。
名義変更に必要な書類を提出
誰がどのような割合で相続するのか確定したら、名義変更の手続をします。
金融機関のホームページ等を参照したり、問い合わせを行ったりするなどして、相続手続に必要となる提出書類の準備をします。
提出書類は金融機関によって異なりますが、主に必要な提出書類の内容としては下記のとおりです。
遺言書がある場合
- 遺言書
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、遺言検認済証明書または遺言書情報証明書(公正証書遺言の場合には検認不要)
- 被相続人の死亡証明書または死亡が確認できる戸籍謄本
- 遺言執行者が家庭裁判所で選任されている場合は遺言執行者選任審判書
- 遺言執行者が就任している場合は遺言執行者の印鑑証明書
- 遺言執行者が選任されていない場合は、相続人全員の印鑑証明書など
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までが分かる戸籍謄本や除籍謄本
- 相続人全員の関係が分かる戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書など
相続人の口座開設・移管手続
金融機関で手続が完了したら、被相続人の口座から相続人の口座へ移管されます。
もし、相続人がまだ証券会社などに相続人名義の口座を開設していない場合には、口座開設の手続も必要となりますので、口座開設に必要な書類一式を準備する必要があります。
金融機関における確認・審査が完了した後、投資信託の受益権は相続人口座へと移管されます。これ以降相続人は、投資信託の受益権を、自己の財産として自由に処分できるようになります。また、すべての相続手続が完了した後、死亡した被相続人の口座は閉鎖されます。
③一部相続人による手続はできない
被相続人が保有していた投資信託を、一部の相続人だけで勝手に解約することはできません。これは、投資信託が準共有財産にあたるためです。相続人全員の同意と署名・押印がなければ、有効な手続とはなりません。
投資信託の相続における注意点
常に価格の変動がおきている
投資信託は、日々価格が変動する金融商品になります。そのため、遺産分割協議時点の価格と売却した時点の価格に大きな差が生じるものもあります。
例えば、遺産分割時には2000万円の価値があった投資信託が、解約時には1000万円まで値下がりしてしまったとしても、投資信託を取得した相続人の自己責任として受け入れなければなりません。
元本償還金や収益分配金も遺産分割の対象となる
被相続人が投資信託の元本償還金や収益分配金を受け取る前に死亡した場合には、元本償還金や収益分配金についても相続の対象に含まれます。
そのため、遺産分割協議の際には、こうした金銭についても相続人同士でどのように承継するか決める必要があります。
解約違約金が発生する可能性がある
投資信託の銘柄によっては、購入後一定期間、解約が制限されているものがあります。
解約制限期間中に投資信託を解約する場合には、解約違約金が発生し、額面の価格よりも大きく目減りした金額しか受け取れない場合があります。
所得税の問題を考慮する
被相続人が投資信託を取得した当時より、売却時の価値のほうが高くなっていた場合、利益となる差額に20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の譲渡所得税が課せられます。
所得税の納付方法については、証券口座において源泉徴収が行われる場合には、それで完了となりますが、源泉徴収が行われないときには確定申告が必要となります。
投資信託と相続税の関係
相続税については、被相続人の死亡日の基準価格で、相続税評価額を計算します。投資信託を含めた相続財産の評価額が、基礎控除額を上回る場合は、相続税の支払いが必要です。
一方で遺産分割時の遺産分割評価額は、相続人間の合意によって任意に評価時点を決められます。
投資信託が遺産に含まれていた場合のワンポイント実務
投資信託の名義変更は、遺産分割の内容が決まってから行いましょう。
名義変更の手続は、遺産分割協議で「誰が取得するか」が確定してから行うのが原則です。
焦って一部相続人の主導で進めてしまうと、他の相続人との信頼関係が壊れてしまい、後に無効主張がされるおそれもあります。
全員の合意を得たうえで進めることが、トラブル予防のカギです。
証券口座は通帳がありません。
被相続人のメールや携帯などを確認するようにしましょう。
オンライン証券で投資信託を保有していた場合、通帳や紙の報告書がないことも多く、遺族が気づけないリスクがあります。確実を期するのであれば、証券保管振替機構に情報開示請求を行い、被相続人名義の口座が保有されている金融機関や証券会社がないかを確認しましょう。
投資信託を複数人で共有相続した場合、解約・移管・売却のたびに全員の同意が必要になります。共有状態は、非常にトラブルが発生しやすいので避けるようにしましょう。
投資信託の評価が「いつ」なのかによって、金額が数百万円単位でズレることも当然にあり得ます。
投資信託も株式と同じで、日々価額が変動するため、遺産分割協議書にどの日を基準に評価したかを明記しておくことで、後日の争いを未然に防げます。
相続税は、死亡日が基準となりますが、遺産分割にあたっては、相続人間で自由にどのタイミングの価額で分けるかを決めることが可能です。
ポイントは、税務と遺産分割実務の違いを理解することで、柔軟な分割ができます。
投資信託の相続は弁護士にご相談ください
投資信託は、仕組みが複雑で、相続の際に誤解を招きやすい金融商品です。
しかし、近年は一般的な資産として広く保有されるようになっており、今後ますます相続実務における重要性が高まっていくと考えられます。
特に、換金処理、遺産分割、税務処理、相続人間の利害調整といった実務の各段階で、法的知識と慎重な対応が求められます。
被相続人がファンドを複数保有しており、相続人の間で意見が分かれ揉めている場合は、弁護士による調整が不可欠になります。
弁護士は、法的な整理を行ったうえで、公平性ある分割案を提案し、全員の合意を取りつけるサポートを行います。
相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、スムーズに手続を進めるためにも、早い段階から弁護士に依頼することが、最良の手段の1つとなります。
投資信託の相続手続に関して、当事務所の弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。
弁護士法人シーライトに依頼することのメリット
- 遺産分割協議の代理・調整が可能:相続人間で意見が食い違った場合でも、法的根拠に基づいて冷静かつ公平な協議をサポートできます。
- 一部相続人による不正解約などの防止:判例を踏まえた正確な手続を進め、他の相続人による不正な解約を防止します。
- 複雑な法的判断が必要な場面への対応:信託受益権の評価や譲渡所得税など税務との関係、複数ファンドが存在する場合の配分、不動産・非上場株式との組合せなど、難しい論点に対しても適切な法的解釈を提供できます。
- 必要に応じて税理士と連携した包括的支援:相続税申告など、他士業と連携したワンストップ対応が可能です。
投資信託は、預貯金などとは違い、どの時点の価格で遺産分割するか、その後の処理はどうするかなど、相続人同士で揉めやすいものでもあります。
相続についてお困りの際は、当事務所にお問い合わせください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
相続の話し合いは、ほんの些細なきっかけから揉めてしまうことが意外と多いです。そのような場面で少しでもお力になるべく、初回相談は無料とさせていただいております。